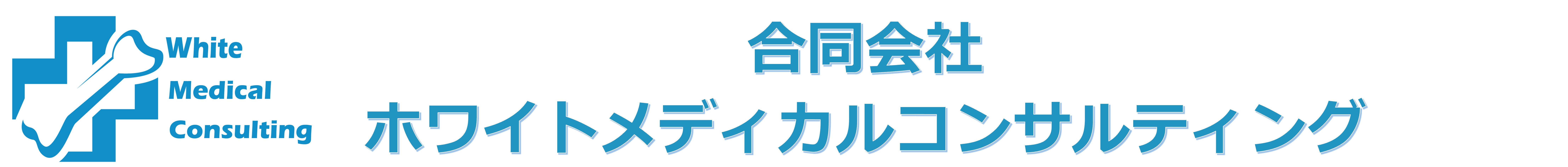症状固定とは?定義や重要性・症状固定後の対応を徹底解説

「医師から症状固定っていわれたけど、症状固定が何かわからない」「症状固定といわれたあとの対応を知りたい」と思っていませんか?
症状固定とは、それ以上治療を続けても症状が回復しない状態のことです。症状固定は事故の損害賠償にも関わるため、症状固定について理解を深め、適切な対応をとる必要があります。
そこでこの記事では、症状固定の概要から症状固定といわれたあとの対応について、整形外科の専門医が詳しく解説していきます。
症状固定について知りたい方や今後後遺障害に関する対応を控えている方は、ぜひ最後までご覧ください。
※「むちうち」という言葉について
このコラムでは、皆様にとって馴染み深く、分かりやすい「むちうち」という言葉を使用して解説を進めますが、これは正式な病名ではなく、あくまで一般的な呼び名(俗語)です。
医療機関における正式な診断名は、「外傷性頚部症候群」となります。
1.症状固定とは?

ここからは、症状固定について以下4つの観点から詳しく解説していきます。
- 症状固定の定義
- 症状固定はなぜ重要なのか
- 症状固定は誰が決めるのか
- 保険会社から「治療費打ち切り」といわれたら
それぞれ確認していきましょう。
1-1.症状固定の定義
症状固定とは、「傷病に対して行われる医学上一般的に承認された治療法方法をもってしても、その効果が期待しない状態で、かつ残存する症状が自然経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」と定義されています。
医療機関で一般的な治療を続けても症状の改善が見られず治療効果が期待できない状態となったときに症状固定と判断されるのです。
症状固定の反対は「治癒」です。治癒は、治療を続けたことで症状がなくなった状態を指す一方で、症状固定は、治療を続けても症状が残存している状態を指します。
そして症状固定と判断された時点で、医師により後遺障害の診断していきます。
1-2.症状固定はなぜ重要なのか
症状固定は、症状固定前後で損害賠償の区分を明確にするために重要です。
症状固定前は「傷害分」として治療費や慰謝料などが請求でき、症状固定後は「後遺障害分」として後遺障害慰謝料や逸失利益が請求可能です。
症状固定後、保険会社からの治療費支払いは停止し、休業損害も支給されなくなります。その後の症状については、後遺障害等級として認定され、認定後に後遺障害分の請求ができます。
1-3.症状固定は誰が決めるのか
症状固定の判断は、主治医である医師がおこないます。医師が前述した「傷病に対して行われる医学上一般的に承認された治療法方法をもってしても、その効果が期待しない状態で、かつ残存する症状が自然経過によって到達すると認められる最終の状態に達した」と判断した時点で、症状固定と診断されるのです。
保険会社や被害者自身が決定するものではなく、医学的な見地から医師が判断します。
関連記事:症状固定は誰が決めるの?保険会社から症状固定といわれたらどうする?
1-4.保険会社から「治療費打ち切り」といわれたら
治療を続ける中で、保険会社から「これ以上治療費を支払うことはできない」といわれることがあります。つまり、保険会社による治療費の打ち切りです。しかし、「治療費打ち切り」は「症状固定」ではありません。
保険会社から治療費の打ち切りを告げられた場合でも、主治医が症状固定と判断していない限りは治療を続けるべきです。
保険会社は治療費の打ち切りのみを言及してきますが、症状固定を決定する権限はありません。まずは主治医に相談し、必要に応じて弁護士などの専門家にアドバイスを求めることが重要です。
2.症状固定となる期間の目安

症状固定となる期間の目安を、以下の症状別にご紹介していきます。
- むちうちによる腰痛やしびれ
- 骨折後の疼痛(とうつう)
- 醜状障害(しゅうじょうしょうがい)
- 高次脳機能障害
- 複数の症状がある
自身に当てはまる症状がないか、確認してください。
2-1.むちうち(外傷性頚部症候群)による頚部痛やしびれ
むちうち(外傷性頚部症候群)による頚部痛やしびの症状固定までの期間は、一律に定められています。基本的に、主治医が医学的に判断するものです。弊社の経験や交通事故を扱う弁護士の先生の情報によると、事故発生時から6-7カ月程度で症状固定と診断されることが多いようです。症状の程度により、症状固定時期は長引く場合もあります。
関連記事:
後遺障害14級の認定を受けるデメリットはある?認定のポイントも解説
労災によるしびれで認定される後遺障害等級や給付金額・認定のポイント
【むちうちの症状の伝え方】重要性やポイント・注意点
2-2.骨折後の疼痛(とうつう)
骨折後の疼痛が症状固定となるまでの期間は、骨折の部位や程度、治療方法によって異なります。一般的に骨折後3~4ヵ月経過しても癒合しない場合を遷延癒合、6~8ヵ月経過しても癒合しない場合を偽関節(≒骨癒合不全)とするとされています、
骨折に対して手術をせず保存治療が行われた場合は偽関節かどうかを判断するのに受傷後6カ月~1年程度はかかります。これくらいの期間で骨癒合が得られたか偽関節となっているかを見極めた上で症状固定とするのが医学的に妥当と考えられるのです。
一方で骨折に対して手術をしてプレートなどの骨内異物を入れた場合は、骨内異物を抜去して後2-3ヵ月後くらいで症状を見極めた上で症状固定とするのが医学的に妥当でしょう。
2-3.醜状障害(しゅうじょうしょうがい)
醜状障害の場合、症状固定までの期間は一律に決まっていません。
例えば肥厚性瘢痕(ケロイド)が残存してしまった場合には、肥厚性瘢痕(ケロイド)に対する形成外科的な治療を行ったのちに症状固定をするのが医学的に妥当でしょう。
6カ月から1年程度で創部の状態を経過観察して創部の瘢痕の状態が変わらなければ、症状固定と判断してもよいでしょう。
2-4.高次脳機能障害
高次脳機能障害の症状固定までの期間は、脳損傷の程度やリハビリの進捗状況によって大きく異なります。
数年単位で回復が見られる場合もあり、症状固定の判断は主治医により慎重におこなわれるのが特徴です。
2-5.複数の症状がある
複数の症状が併発している場合、症状固定までの期間は、各症状の回復状況や相互作用によって複雑になります。そのため、個別の症状ごとに評価をおこない、総合的に判断する必要があります。
一般的な目安はなく、ケースバイケースで異なります。
3.症状固定といわれたあとの対応・手続き
主治医から症状固定といわれたあとの対応次第では、損害賠償に影響が出る可能性があり、十分に検討する必要があります。
ここからは、症状固定と判断されたあとの対応について詳しく解説していきます。
3-1.通院が必要な場合は主治医に相談する
症状固定と診断されたあとも、通院が必要な場合は主治医に相談してください。症状固定と診断されたからと言って、通院して治療を受けられなくなるわけではありません
症状の状態に応じて、主治医に治療の継続を相談しましょう。
3-2.後遺障害認定の手続きを進める
症状固定後は、後遺障害認定の手続きを進めましょう。後遺障害の認定をされることで、適切な補償や支援を受けられます。
後遺障害認定には、「事前認定」と「被害者請求」という2つの方法があります。
3-2-1.事前認定
事前認定は、加害者側の保険会社が被害者の同意を得て、医療記録や診断書を基に後遺障害の等級を認定する方法です。事前認定の場合は、被害者自身が申請する必要がなく、比較的スムーズに進行することが多いです。
事前認定については、以下の記事でさらに詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
関連記事:後遺障害の事前認定とは?メリット・デメリットや異議申し立ての方法
3-2-2.被害者請求
被害者請求は、被害者自身が必要な書類を収集し、後遺障害等級の認定を申請する方法です。
自分で手続きをおこなうため、事前認定と比較して時間や労力がかかります。ですが、自身で正確な証拠を集められたり、加害者側の保険会社との交渉を直接おこなえたりすることから、希望する後遺障害の等級認定を受けやすいというメリットもあります。
4.症状固定後の被害者請求をおこなうときは医学的な証拠が必要
症状固定後に被害者請求をおこなう際、医学的な証拠は不可欠です。
医学的な証拠は、症状の程度や後遺障害の有無を客観的に示すものです。これらの証拠がなければ、後遺障害等級の認定や適切な賠償額の算定が難しくなります。
そのため症状固定後は、以下のような客観性の高い医学的証拠を集めましょう。
- 医師による診断書
- 各種検査結果
- リハビリの記録
- 症状経過記録
- 医学意見書
早期の検査や診断によって、地道に証拠を収集していくことが大切です。
関連記事:交通事故の後遺障害における医学意見書の役割やメリットとは?
4-1.医学意見書の作成なら弊社にお任せください
医学意見書の作成なら、弊社にお任せください。
医学意見書とは、主治医とは別の専門医が、中立的立場で診療録・診断書・画像検査を精査し、正確かつ詳細な医学的見解を示した書類のことで、事故後の賠償請求や裁判において重要な医学的証拠となります。
弊社では症状固定時期についても診療録や画像等の資料を基に医学意見書を作成した経験があるのです。
弊社には、ほぼすべての診療科の専門医が在籍しており、医学意見書作成に最適な診療科の選定は医師自身がおこないます。そのため、症状に関する客観的で正確な判断が可能です。
医学意見書作成をご検討の際は、ぜひ弊社にご相談ください。
※弊社は弁護士の先生からのお問い合わせに対してのみ、サービスを承っております。そのため交通事故の被害にあった当事者の方は、必ず代理人弁護士の先生を通してご連絡頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。
5.症状固定に関するよくある質問
最後に、症状固定に関するよくある質問とその回答をご紹介していきます。
5-1.症状固定は誰が決めますか?
症状固定は、主に担当医が決定します。事故後の症状や検査結果を総合的に評価し、主治医がこれ以上の改善が期待できないと判断した場合に、症状固定と判断されます。
5-2.症状固定といわれたらどうすればいいですか?
症状固定といわれたら、まずは主治医からその理由や今後の治療方針について詳しく説明を受けましょう。また、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい症状固定時の症状を正確・適切に記載してもらえるように主治医へ伝えましょう。
5-3.医師の症状固定に納得できなかったらどうすればいいですか?
医師の症状固定の判断に納得できない場合、まずは医師に対して疑問や不安を率直に伝え、詳細な説明を求めましょう。それでも解決しない場合は、他の医師の意見を聞くセカンドオピニオンを受けることも可能です。
患者の権利として、自身の健康状態や治療方針について十分な情報を得ることが重要です。
6.まとめ
この記事では、症状固定の概要から症状固定と主治医からいわれたあとの対応について解説しました。
症状固定とは、「傷病に対して行われる医学上一般的に承認された治療法方法をもってしても、その効果が期待しない状態で、かつ残存する症状が自然経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」のことで、症状固定前後で損害賠償の区分を明確にするために重要な要素となっています。
主治医から症状固定といわれたら、通院が必要な場合は主治医に相談し、後遺障害認定の手続きを進めるようにしましょう。
合同会社ホワイトメディカルコンサルティングでは、後遺障害認定の被害者請求時に有効な証拠となる医学意見書の作成をおこなっております。症状固定時期についても診療録や画像等の資料を基に判断させていただくことが可能となっております。
後遺障害を抱え医学意見書が必要な状況にある方は、是非弊社にご依頼ください。
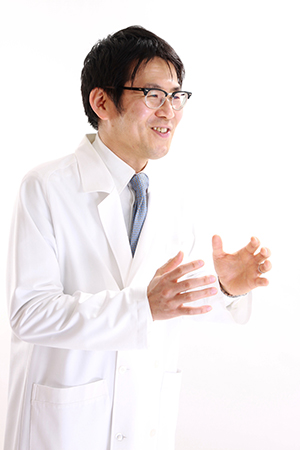
このコラムの著者
白井 康裕
【経歴・資格】
・日本専門医機構認定 整形外科専門医
・日本職業災害医学会認定 労災補償指導医
・日本リハビリテーション医学会 認定臨床医
・身体障害者福祉法 指定医
・医学博士
・日本整形外科学会 認定リウマチ医
・日本整形外科学会 認定スポーツ医
2005年 名古屋市立大学医学部卒業。
合同会社ホワイトメディカルコンサルティング 代表社員。
医療鑑定・医療コンサルティング会社である合同会社ホワイトメディカルコンサルティングを運営して弁護士の医学的な業務をサポートしている。
【専門分野】
整形外科領域の画像診断、小児整形外科、下肢関節疾患