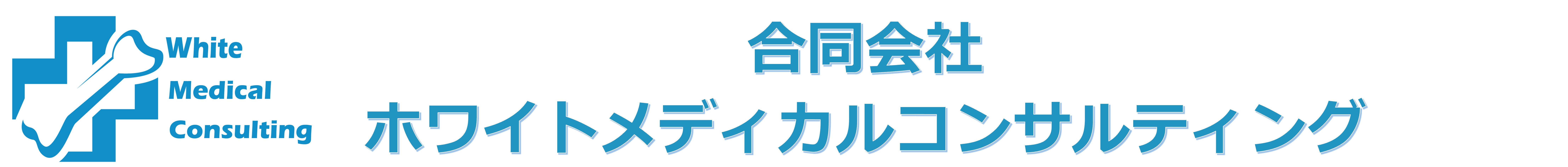むちうちの症状が出るまでの期間は?遅れて出る理由と早期対応の重要性
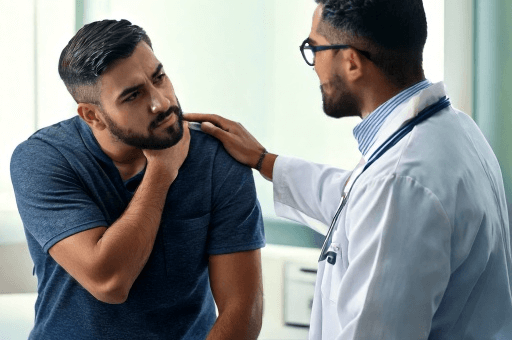
「交通事故に遭った直後は何ともなかったのに、翌朝起きたら首が痛くて動かない…」
そんな経験に、今まさに不安を感じていませんか。むちうち(外傷性頚部症候群)の症状は、事故直後ではなく、数時間や数日経ってから現れることはよくあることです。症状を放置すると、後遺障害に繋がる恐れもあります。
そこでこの記事では、むちうちに対する不安を解消する以下の情報を、整形外科医が網羅的に解説します。
- むちうちの症状が出るまでの期間
- 症状を和らげる正しい対処法
- 万が一のための後遺障害認定までの流れ
むちうちの症状が出て不安に思っている方や、症状が出たあとにまず何をすべきか分からないという方は、ぜひ最後までご覧ください。
※「むちうち」という言葉について
このコラムでは、皆様にとって馴染み深く、分かりやすい「むちうち」という言葉を使用して解説を進めますが、これは正式な病名ではなく、あくまで一般的な呼び名(俗語)です。
医療機関における正式な診断名は、「外傷性頚部症候群」となります。
1.むちうち(外傷性頚部症候群)は症状が多様
むちうち(外傷性頚部症候群)の症状としてイメージしやすいのが首の痛みですが、実際にはそれ以外にもさまざまな症状が出ます。以下のような症状も、むちうちの症状の一つです。
- 首の痛み
- 肩の痛み
- 頭痛
- 四肢のしびれ
- めまい、耳鳴り
むちうちは、事故などの衝撃による頚部への外傷により頚部が前屈・後屈を強制され、軟部組織損傷をもたらすことにより症状を発症するとされています。
首以外の場所に症状が出ても、むちうちが原因である可能性を疑い、早めに専門医に相談することが大切といえます。
関連記事:【むちうちの症状の伝え方】重要性やポイント・注意点
2.むちうち(外傷性頚部症候群)の症状が出るまでどれくらいの期間がある?
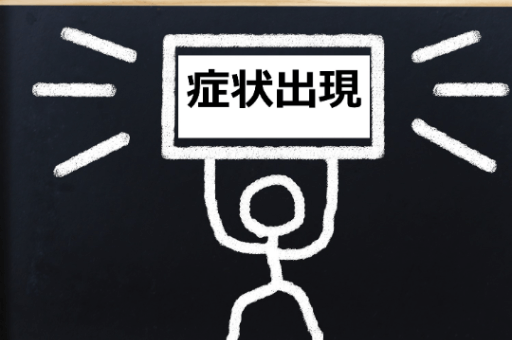
むちうちの症状は、事故などの受傷当日ではなく、数時間から数日経ってから現れることが多いです。事故直後は、心身が興奮状態にあるため、痛みを感じにくいことがあるためです。
受傷から時間が経ち、気持ちが落ち着いてくるにつれて、徐々に頚部周囲の痛みや不調として自覚するようになります。
そのため、「事故の直後に痛くないから大丈夫」と自己判断するのは大変危険です。
2-1.受傷当日〜受傷翌日が一般的
むちうちの症状は6割強が6時間以内、9割が24時間以内に発症すると医学論文で報告されています。それゆえ、症状が現れる最も一般的なタイミングは、事故などに遭った当日中、とくに夕方から夜にかけて、またはその翌日です。
受傷から時間が経って体がリラックスしてくると、頚部の軟部組織の損傷した部位の痛みやこりといった症状を感じ始めます。「朝起きたら、首が痛くて全く動かせなくなっていた」というケースは、非常に多く見られます。
事故当日に何もなくても、決して油断しないようにしてください。
2-2.受傷翌日から痛みが強まる
むちうちの症状は、受傷翌日から数日後にかけて、徐々に痛みが強まることがよくあります。頚部の軟部組織の損傷した部位の炎症が、時間の経過とともにピークに達するためです。
最初は「少し首が張るな」程度だったのが、翌日には強い首の痛みになる、ということも少なくありません。
症状の変化を注意深く観察し、悪化するようであればすぐに医療機関を受診しましょう。
2-3.ほとんどの場合72時間以内に症状が出る
むちうち(外傷性頚部症候群)の患者の症状の発症時期を調べた医学論文では、受傷してから72時間以内に100%の患者に症状が現れることが報告されています。もちろん、症状の手術現時期には個人差はありますが、実際に、交通事故の治療において、事故との因果関係を証明するうえでも、この「72時間」は一つの目安とされています。
事故に遭った際は、たとえ無症状でも、最低でも2〜3日はご自身の体調に細心の注意を払うようにしましょう。
3.むちうち(外傷性頚部症候群)は症状が出てからいつまで続く?

むちうちの症状が続く期間は、一般的には数週間から約3カ月以内に改善に向かうとされています。
しかし、むちうちの患者を追跡した医学論文では、受傷後3年で症状が完全に消失した割合は5割弱という報告もあります。実際にむちうちの患者さんにおいては、長期に頚部痛などの症状が持続するかたも日々の診療の中で経験します。
早期に適切な治療を開始し、医師の指示通りに通院を続けることが、症状の長期化を防ぐうえで最も重要です。
4.受傷後72時間以内にむちうち(外傷性頚部症候群)の症状が出たらすぐに医療機関を受診する
事故などの受傷後72時間以内にむちうちの症状が出た場合は、たとえ軽症であっても、必ず整形外科をはじめとした医療機関を受診してください。
これは、正確な診断を受けるためだけでなく、交通事故の場合、その後の治療費や慰謝料などの賠償請求において、「事故と症状の因果関係」を証明するために極めて重要だからです。受診が遅れると、保険会社から「その症状は事故とは関係ない」と主張され、治療費の支払いを拒否される可能性があります。
ご自身の体を守りながら、正当な補償を受けるためにも、迅速な受診が不可欠です。
4-1.受傷1ヶ月後以降の痛みとむちうちの因果関係はないと考えるべき
前述したとおり、受傷してから72時間以内に100%の患者に症状が現れることが報告されているため、事故から1カ月以上経ってから初めて痛みが出た場合、その症状と事故との因果関係を医学的に証明するのは、非常に困難になると考えるべきです。
一般的に、事故による外傷の症状は、数日以内に現れるとされています。そのため、事故から長期間が経過した後に現れた痛みは、事故とは別の日常生活上の原因によるものだと、相手方の保険会社などから強く主張される可能性が高いのです。
もちろん例外はありますが、正当な治療や補償を受けるために、事故後少しでも体に異変を感じたらすぐに医療機関を受診するという初期対応が何よりも大切になります。
関連記事:後遺障害が認定されない理由とは?認定されなかったときの対処法も解説
5.むちうち(外傷性頚部症候群)の症状が出てから後遺障害認定を受けるまでの流れ
むちうちの症状が出た場合、後遺障害認定を受けることで、慰謝料や逸失利益(後遺症がなければ、将来得られたはずの収入)を請求することができます。しかし、正しい手順にて手続きを進めないと、正当な後遺障害認定を受けられず、場合によっては慰謝料が減額になる可能性も否定できません。
そのためむちうちの症状が出たあとは、以下の手順に沿って後遺障害認定を受けるようにしてください。
- 医療機関を受診する
- 治療を継続的におこなう
- 症状固定後に後遺障害診断書を作成してもらう
- 後遺障害等級認定を申請する
- 示談交渉をおこなう
一つずつ解説していきます。
5-1.医療機関を受診する
事故に遭い、むちうちの症状が出たら、まず最初に必ず整形外科などの医療機関を受診してください。適切な治療を受けるためだけでなく、交通事故と症状との因果関係を客観的に証明するための、最も重要な第一歩です。
前述もしたように、医療機関の受診が遅れると、あとからむちうちの症状を訴えても事故との関連を疑われてしまう可能性があります。
事故直後に痛みが軽くても、決して自己判断せず速やかに医師の診断を受けることが、後遺障害認定を目指すうえで重要です。
5-2.治療を継続的におこなう
次に、医師の指示に従い、痛みや不調が改善するまで継続的に通院し治療を受けましょう。
通院の頻度や期間は、むちうち症状の重さを客観的に推定できる材料となります。痛みを我慢して通院を中断したり、不定期になったりすると、「症状は軽かった」と判断されかねません。
診察時には、痛みやしびれなどの具体的な症状を正確に医師に伝えることも大切です。一貫した治療の継続が、症状の存在を証明し、正当な後遺障害等級認定につながります。
関連記事:むちうちの治療期間はどの程度?治療期間が慰謝料に与える影響を解説
5-3.症状固定後に後遺障害診断書を作成してもらう
治療を続けても症状の改善が見込めなくなった「症状固定」の段階で、担当の医師に「後遺障害診断書」を作成してもらいます。
後遺障害診断書は、後遺障害等級を認定するうえで、最も重要視される医学的な証拠です。これまでの治療経過や検査結果、そして現在残っている症状(痛み、しびれなど)を、客観的かつ具体的に記載してもらいましょう。
医師に症状を正確に伝え、適切な内容の診断書を作成してもらうことが、認定の鍵を握ります。
関連記事:症状固定は誰が決めるの?保険会社から症状固定といわれたらどうする?
5-4.後遺障害等級認定を申請する
作成された後遺障害診断書などの必要書類を、自賠責保険の調査機関に提出し、後遺障害等級の認定を申請します。
後遺障害等級認定の申請には、相手方の保険会社に手続きを任せる「事前認定」と、被害者自身(または代理人弁護士)が必要書類を全て集めて申請する「被害者請求」の2つの方法があります。
事前認定は、加害者側の任意保険会社に手続きの全てを任せるため被害者の手間は少ないものの、透明性には欠けるといえます。一方被害者請求は、被害者自身(または代理人の弁護士)が有利な証拠を集めて直接申請するため、手間はかかりますが、より適正な等級認定を目指せる方法です。
どちらかの方法で後遺障害等級認定を申請することで、あなたの症状がどの等級に該当するかが公式に判断されます。
関連記事:後遺障害の事前認定とは?メリット・デメリットや異議申し立ての方法
5-5.示談交渉をおこなう
後遺障害等級の認定後、その等級をもとに、後遺障害慰謝料などを含めた最終的な賠償額について、相手方の保険会社と示談交渉をおこないます。認定された等級は、賠償額の算定において重要な基準となります。
そして、保険会社から提示された金額が、必ずしも法的に妥当な額とは限りません。弁護士に依頼すると、裁判基準にもとづいた、より正当な賠償金を請求することが可能です。
示談交渉で合意した内容で、交通事故に関する全ての損害賠償問題が解決となります。
6.つらいむちうち(外傷性頚部症候群)の症状を抑える方法
最後に、つらいむちうちの症状を抑える方法を以下2つの時期に分けてそれぞれ解説していきます。
- 急性期(受傷直後〜3日程度)
- 慢性期(痛みが少し落ち着いてから)
また、痛みがある際にやってはいけないことも解説していますので、順番に確認してください。
6-1.急性期(受傷直後〜1週間程度)
受傷直後〜3日程度のむちうち急性期には、以下2つのポイントを押さえてください。
- 痛み止めを服用し安静にする
- 痛みが出る動作を避ける
それぞれ解説します。
6-1-1.痛み止めを服用し安静にする
急性期の強い痛みに対しては、医師から処方された痛み止めや湿布を使用し、我慢せず痛みを沈静化することが最も重要です。
痛みを我慢すると、無意識に体に力が入り、首周りの筋肉がさらに緊張してしまいます。薬で痛みをコントロールしながら、首に負担のかかる長時間のデスクワークやスマートフォンの操作は避け、ゆっくりと休みましょう。
痛みを和らげ、安静を保つことで、損傷した組織の回復を促します。
6-1-2.痛みが出る首の動作を避ける
日常生活や仕事で首を動かさなくてはいけないこともあるかと思います。しかし、首をひねると痛いということは首の損傷部に負荷がかかっていることを意味します。できるだけ、首は動かさないで腰から動かすなどの注意をして首の負荷を減らす動きを心がけましょう。そういう意味では急性期のみ頚椎カラーを装着することも選択しても良いのです。
6-2.慢性期(痛みが少し落ち着いてから)
むちうちの痛みが少しずつ落ち着く「慢性期」では、以下2つの方法を試してみてください。
- 痛みのない範囲で首を動かす
- リハビリをおこなう
一つずつ見ていきましょう。
6-2-1.痛みのない範囲で適度に首を動かす
痛みがあるからといって、長い期間にわたり首を安静にすることは現在有効性が否定されてきています。ストレッチなど適度に首を動かすことが有効であるとされています。痛みが落ち着いてきた慢性期には、適度に首を動かすことを心がけましょう。長期間頚椎カラーを装着して首を動かさないことも現在は有効ではないとされています。
6-2-2.リハビリテーションをおこなう
病院では事故後1週間以上経過した慢性期にリハビリテーションを介することが多いです。理学療法士とマンツーマンで症状をとるためのモビリゼーションやマニピュレーション,筋力訓練ストレッチ,可動域訓練などの指導を、無理のない範囲受けられます。資格のある専門の理学療法士と行うことで有効な治療となるでしょう。
6-3.やってはいけないこと
むちうち(外傷性頚部症候群)の症状があるときに、良かれと思っておこなった行為が、かえって回復を遅らせたり、症状を悪化させたりすることがあります。なかでも、以下4つのNG行動を避けてください。
- 自己判断でマッサージや整体を受ける
- 痛みを我慢する
- 飲酒する
- 症状を放置する
一つずつ解説します。
6-3-1.自己判断でマッサージや整体を受ける
自己判断でマッサージや整体、カイロプラクティックといった施術を受けることは、絶対に避けてください。
特に、炎症が残っている急性期に、患部を強く揉んだり、首の骨をボキボキと鳴らしたりするような強い刺激を加えると、症状を悪化させる危険性が高いです。
施術を受ける場合は、必ず事前に主治医に相談し、許可を得てからにしましょう。
6-3-2.痛みを我慢する
痛みが出ているということは、体から「これ以上動かさないで」という危険信号が出ている証拠です。そのため、痛みは決して我慢してはいけません。
痛みを我慢して仕事や運動を続けると、痛みが長引く原因にもなるでしょう。
痛みが強い場合は、無理をせず頚部を安静にて、処方された薬を服用するなど、適切に対処することが大切です。
6-3-3.飲酒する
むちうちの急性期で痛みや炎症がある期間は、飲酒は控えるようにしてください。
アルコールには、血管の拡張と血行を促進する作用があります。そのため、とくに炎症が強い急性期に飲酒をすると、痛みが悪化してしまう可能性が高いです。
急性期にはお酒を控えるようにしましょう。
6-3-4.症状を放置する
むちうちの痛みが残存しているにもかかわらず、「大したことはないだろう」と症状を放置することは、症状の慢性化や後遺障害につながる、最も避けるべき行為です。
適切な初期対応と治療をおこなわないと、痛みがずっと残ってしまったりして、長期的に生活に支障をきたす場合があります。
事故に遭って首の周りに症状がある場合は、まずは一度医療機関を受診し、症状が続く場合は、きちんと治療を続けることが何よりも重要です。
7.まとめ
この記事では、むちうち(外傷性頚部症候群)の症状が現れるまでの期間、症状を抑えるための時期別の対処法、そして後遺障害認定までの流れを詳しく解説しました。
最も重要なのは、「事故直後に痛くないから大丈夫」と自己判断せず、事故後72時間以内に少しでも首の周りの症状があれば、すぐに整形外科を受診することです。その初動が、あなたの体の健康を守り、万が一症状が長引いた場合の正当な権利を守ることにつながります。
正しい知識を持ち、焦らず、専門家と相談しながら、適切な治療と手続きを進めていきましょう。
合同会社ホワイトメディカルコンサルティングでは、むちうちの後遺障害認定に有効な証拠となる医学意見書の作成をおこなっております。
むちうちの症状を抱え医学意見書が必要な状況にある方は、是非弊社にご依頼ください。
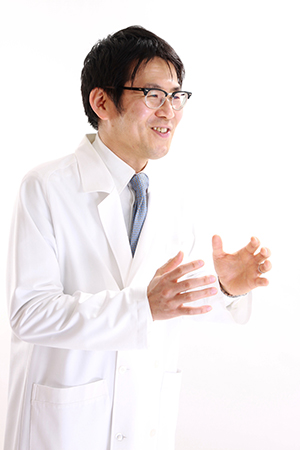
このコラムの著者
白井 康裕
【経歴・資格】
・日本専門医機構認定 整形外科専門医
・日本職業災害医学会認定 労災補償指導医
・日本リハビリテーション医学会 認定臨床医
・身体障害者福祉法 指定医
・医学博士
・日本整形外科学会 認定リウマチ医
・日本整形外科学会 認定スポーツ医
2005年 名古屋市立大学医学部卒業。
合同会社ホワイトメディカルコンサルティング 代表社員。
医療鑑定・医療コンサルティング会社である合同会社ホワイトメディカルコンサルティングを運営して弁護士の医学的な業務をサポートしている。
【専門分野】
整形外科領域の画像診断、小児整形外科、下肢関節疾患