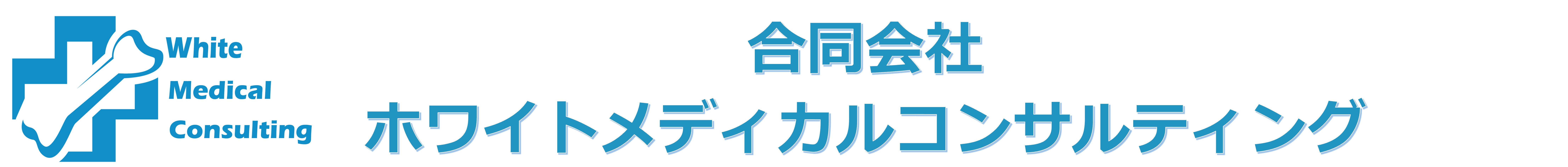症状固定は誰が決めるの?保険会社から症状固定といわれたらどうする?

「症状固定は誰が決めるの?」「保険会社から症状固定と言われたけどどうすればいい?」と疑問に思っていませんか?
結論、症状固定を決めるのは医師です。医師以外の保険会社や被害者本人が決めることはできません。
この記事では、以下の内容を中心に解説していきます。
- 症状固定は誰が決めるのか?
- 保険会社から症状固定と言われたあとの対応
症状固定と言われたけどどうすればいいかわからない方や、症状固定の判断に迷われている方は、ぜひ最後までご覧ください。
1.症状固定は誰が決めるのか?
症状固定の判断は、必ず主治医である医師がおこないます。
主治医によって、医学的な見地から「これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない」と判断された時点で、症状固定とされます。
1-1.症状固定の定義について
症状固定とは、「傷病に対して行われる医学上一般的に承認された治療法方法をもってしても、その効果が期待しない状態で、かつ残存する症状が自然経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」と定義されています。
医療機関で一般的な治療を続けても症状の改善が見られず治療効果が期待できない状態となったときに症状固定と判断されるのです。
症状固定の判断は、主治医が患者の治療経過や症状の状態を総合的に評価しておこなわれます。
関連記事:症状固定とは?定義や重要性・誰が決めるのか・症状固定後の対応
1-2.主治医や保険会社が勝手に症状固定を決めることはできない
前述したように、症状固定の判断は医師が医学的な見地をもとにおこなうものであり、保険会社や被害者自身が勝手に決めることはできません。
また、被害者にしかわからない自覚症状を無視して、医師が独断で決めるものでもありません。症状固定の判断は、あくまで医師が被害者の自覚症状と医学的・他覚的所見を基に治療効果を加味したうえでおこなわれます。
1-3.症状固定時期で争いが起きたときは裁判所が決めることもある
症状固定の時期について、医師と保険会社、被害者の間で意見が分かれることがあります。そのような場合、最終的には裁判所が判断を下すことになります。
裁判所は、医師の診断書や治療経過、症状の状態などを総合的に評価して、症状固定の時期を決定します。そのため、症状固定の時期について争いが生じた場合は、専門家である弁護士に相談することが望ましいです。
2.保険会社から症状固定を促される場合もある
症状固定の時期を主治医以外が決めることはできないですが、場合によっては保険会社から症状固定を促されるケースもあります。
ですが、症状固定の判断は医師がおこなうものであり、保険会社が勝手に決めることはできません。
保険会社から症状固定を促された場合は、保険会社の提案にすぐに応じるのではなく、主治医と相談して適切な対応を取りましょう。
2-1.保険会社から症状固定を促されるのはなぜか
保険会社が症状固定を促す理由は、「支払いを早く終わらせて損害賠償額を抑えるため」です。
治療が長引くと、その分だけ治療費や慰謝料が増える可能性があります。そのため、保険会社は一定の期間が経過すると、損害倍書額を少しでも抑えるために症状固定を提案してくることがあるのです。
2-2.症状固定前後で加害者が支払うお金一覧
症状固定の前後では、加害者が支払うべき賠償項目が変わります。
| 症状固定前の賠償項目 | 治療費 通院交通費 休業補償 入通院慰謝料など |
| 症状固定後の賠償項目 | 後遺障害慰謝料 逸失利益(後遺障害によって将来得られなくなった収入の補償) 介護費など |
1日でも早く症状固定と判断されれば、保険会社が支払う治療費や慰謝料などがその分減ります。そのため、保険会社から症状固定を促されることがあるのです。
また、症状固定の時期を早めると、適切な後遺障害等級の認定を受けにくくなる場合もあります。
このように、症状固定の時期によって賠償内容が大きく変わるため、適切なタイミングでの判断が重要です。
3.保険会社から症状固定と言われても安易に受け入れない

保険会社から症状固定と言われても、安易に受け入れないようにしてください。その理由は以下の2点です。
- 適切な後遺障害認定を受けられないことがある
- リハビリや治療の費用を受け取れない可能性がある
それぞれ解説していきます。
3-1.理由①適切な後遺障害認定を受けられないことがある
保険会社の提案に従って早期に症状固定を受け入れてしまうと、適切な後遺障害認定を受けられない可能性があります。
症状固定を早めてしまうと、後遺障害が正確に評価されず、適切な補償を受けられない原因となります。
後遺障害の等級認定は症状固定後におこなわれるため、適切な時期を見極めることが重要です。そのため、症状固定の判断は主治医と十分に相談し、慎重におこないましょう。
関連記事:後遺障害が認定されない理由とは?認定されなかったときの対処法も解説
3-2.理由②リハビリや治療の費用を受け取れない可能性がある
症状固定後は、原則として治療費やリハビリ費用を請求できなくなります。保険会社が治療費の支払いを打ち切るために症状固定を促すことがありますが、これに応じると、必要な治療に関する費用を受け取れなくなる恐れがあります。
そのため、治療の継続が必要か、医師と十分に話し合いましょう。
4.保険会社から症状固定と言われたあとの対応
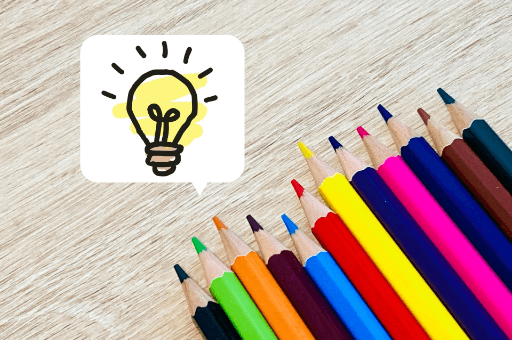
保険会社から症状固定といわれたら、適切な対応をとらなければなりません。以下の手順に従って、対応を進めてください。
- まずは主治医に相談する
- 治療が必要と判断されたら治療を続ける
- 主治医から症状固定と言われたら後遺障害認定の手続きを進める
詳しく解説していきます。
4-1.まずは主治医に相談する
保険会社から症状固定を提案された場合、まずは主治医に相談しましょう。
症状固定の判断は、患者の治療経過や症状の改善状況を最も理解している主治医がおこなうものだからです。保険会社の提案を鵜呑みにすることなく、主治医に意見を求めてください。
ただし、主治医も交通事故の患者の診療経験が少ないケースがあります。保険会社が行ってきたからという理由で、患者に症状固定をするように勧めてくる医師がいることは事実なのです。症状が続いていて、治療効果が十分でないときは主治医に自分の病状をしっかり伝える必要があるでしょう。
4-2.治療が必要と判断されたら治療を続ける
主治医が治療を継続するべきと判断した場合は、その判断に従いましょう。症状固定前に治療を中断すると、後遺障害の認定や補償に影響する可能性があるためです。
特に、外傷性頚部症候群(むち打ち)などの痛み(神経症状)は、継続的な治療が必要な場合が多く、主治医の指示に従って適切な治療を受けることが重要です。
4-3.主治医から症状固定と言われたら後遺障害認定の手続きを進める
主治医から症状固定と診断された場合は、後遺障害認定の手続きを進めてください。後遺障害等級の認定を受けることで、適切な補償を受けられるようになります。
後遺障害認定の手続きでは、後遺障害診断書などの必要書類を準備したうえで、自賠責保険会社へ申請をおこないます。
申請方法は、保険会社を通じておこなう「事前認定」と、被害者自身がおこなう「被害者請求」の2種類です。自身の状況に応じて、適切な方法を選択しましょう。
関連記事:後遺障害の事前認定とは?メリット・デメリットや異議申し立ての方法
4-3-1.後遺障害認定の手続きで必要な書類
後遺障害認定の手続きの進め方によって、必要となる書類が異なります。
| 書類 | 事前認定 | 被害者請求 |
| 後遺障害診断書 | ⚪︎ | ⚪︎ |
| 診療報酬明細書 | × | ⚪︎ |
| 交通事故証明書 | × | ⚪︎ |
| 事故発生状況報告書 | × | ⚪︎ |
| 保険金請求書 | × | ⚪︎ |
| 休業損害証明書 | × | ⚪︎ |
| 通院交通費明細書 | × | ⚪︎ |
| 委任状・委任者の印鑑証明書 | × | ⚪︎ |
| 印鑑証明書 | × | ⚪︎ |
| レントゲン写真などの検査結果 | × | ⚪︎ |
これらの書類を漏れなく準備し、提出することで、後遺障害等級の認定を受けることが可能になります。
関連記事:後遺障害等級認定の期間とは?目安より遅れる理由や対処法も解説
5.症状固定のベストなタイミングは弁護士に相談するのがおすすめ
主治医に症状固定を判断してもらうベストなタイミングは、以下のような理由から弁護士に相談するのがおすすめです。
- 主治医は損害賠償に関する知識がない
- 示談に向けた準備を的確におこなえる
- 主治医と連携をとってもらえる
詳しく解説していきます。
5-1.主治医は損害賠償に関する知識がない
主治医は、患者の治療をおこなう専門家であり、損害賠償や後遺障害認定に関する法律的な知識は持ち合わせていないことが多いです。そのため、医学的な観点だけで症状固定の時期を判断すると、損害賠償の面で損する可能性も否定できません。
一方弁護士は、損害賠償に関する専門知識を持つ弁護士であれば、最適なタイミングでの症状固定をサポートをしてくれます。
5-2.示談に向けた準備を的確におこなえる
弁護士に相談することで、示談に向けた準備を的確におこなうことが可能です。保険会社との交渉では、適切な証拠や書類が必要となりますが、弁護士はこれらの準備をサポートしてくれます。
また、過去の判例や法律に基づいたアドバイスを受けることで、示談交渉を有利に進められるようになります。
5-3.主治医と連携をとってもらえる
弁護士は、主治医と連携をとりながら、症状固定のタイミングや後遺障害認定に必要な書類の準備をサポートしてくれます。主治医が損害賠償に関する知識を持っていない場合でも、弁護士が間に入ることで、主治医との間で後遺障害の認定に関する適切な情報共有が可能となるのです。
これにより、後遺障害認定の申請や示談交渉をスムーズに進めることができます。
6.【弁護士の先生へ】症状固定後の医学意見書作成は弊社までご相談ください
症状固定後の医学意見書作成は、合同会社ホワイトメディカルコンサルティングへお任せください。
症状固定後の後遺障害等級認定手続きにおいて、以下のような課題に直面されることはないでしょうか。
- 提出された診断書や画像所見だけでは、後遺障害の存在や程度を十分に立証できない
- 主治医の先生が意見書作成に協力的でない、または専門外のため的確な記載が難しい
- 膨大な医療記録を読み解き、医学的な争点を整理する時間がない
- より客観的で説得力のある医学的根拠を示したい
このような場合、専門的な知見に基づいた「医学意見書」が、適正な後遺障害等級認定を得るための強力な武器となり得ます。
弊社には、ほぼすべての診療科の専門医が在籍しており、医学意見書作成に最適な診療科の選定は医師がおこないます。そのため、症状に関する客観的で正確な判断が可能です。
医学意見書作成をご検討の際は、ぜひ弊社にご相談ください。
※弊社は弁護士の先生からのお問い合わせに対してのみ、サービスを承っております。そのため事故の被害にあった当事者の方は、必ず代理人弁護士の先生を通してご連絡頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。
関連ページ:交通事故や医療過誤等の医学意見書作成
7.症状固定は誰が決めるのかに関するよくある質問
最後に、「症状固定はだれが決めるのか」に関連するよくある質問に回答していきます。
7-1.Q. 結局、症状固定は誰が決めるのですか?
症状固定の判断は、主治医である医師がおこないます。医師は、患者の症状の経過や検査結果、治療の効果などを総合的に評価し、これ以上の回復が見込めないと判断した時点で症状固定と診断します。
また、症状固定には被害者の自覚症状や治療効果も考慮されるため、医師と患者が相談しながら決定されるのが一般的な流れです。
7-2.Q.主治医の先生が「症状固定」と言えば、それで決まりですか?
主治医が「症状固定」と判断した場合でも、患者が症状の改善を感じている場合は、治療の継続を希望することも可能です。
しかし、最終的には主治医が症状固定の判断をするため、治療継続を希望する際には医師と十分に相談する必要があるでしょう。
7-3.Q.保険会社から「症状固定」だと言われましたが、従うべきですか?
保険会社から症状固定だと言われても、従う必要はありません。症状固定の判断は医師がおこなうものであり、保険会社が一方的に決定することはできないためです。
治療の継続が必要と判断される場合は、医師と相談し、必要に応じて弁護士に相談することも検討しましょう。
7-4.Q.症状固定の適切な期間が知りたいです。
原則として、症状固定の時期は、外傷の種類や治療の経過によって異なります。
弊社の実績や交通事故案件を多く扱っている弁護士の先生からのお話を考慮すると、治療期間はむちうち(外傷性頚部症候群)においては、通院期間は6〜7ヵ月以上、通院頻度は週1回程度以上で認定される可能性が高くなっているようです。
しかし、この期間が本当に適切なのかは後遺障害の認定基準が非公開のため、はっきりとはわかりません。個々の症状や回復状況によって異なるため、主治医と相談しながら判断しましょう。
※「むちうち」という言葉について
「むちうち」という言葉は正式な病名ではなく、あくまで一般的な呼び名(俗語)です。
医療機関における正式な診断名は、「外傷性頚部症候群」となります。
8.まとめ
症状固定のタイミングは、主治医である医師によってのみ判断されます。そのため、保険会社や被害者本人が独断で症状固定を決めることはできません。
保険会社は、賠償額の負担を下げるために症状固定を促してくることがありますが、安易に受け入れてはいけません。以下の手順で、適切な対応を進めてください。
- まずは主治医に相談する
- 治療が必要と判断されたら治療を続ける
- 主治医から症状固定と言われたら後遺障害認定の手続きを進める
合同会社ホワイトメディカルコンサルティングでは、後遺障害認定の被害者請求時に有効な証拠となる医学意見書の作成をおこなっております。症状固定時期についても診療録や画像等の資料を基に判断させていただくことが可能となっております。
後遺障害を抱え医学意見書が必要な状況にある方は、是非弊社にご依頼ください。
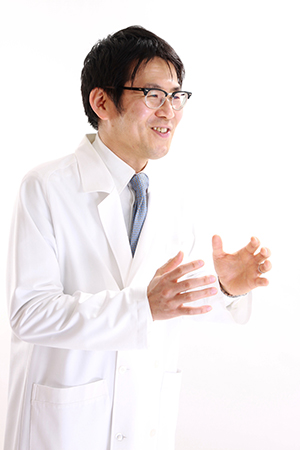
このコラムの著者
白井 康裕
【経歴・資格】
・日本専門医機構認定 整形外科専門医
・日本職業災害医学会認定 労災補償指導医
・日本リハビリテーション医学会 認定臨床医
・身体障害者福祉法 指定医
・医学博士
・日本整形外科学会 認定リウマチ医
・日本整形外科学会 認定スポーツ医
2005年 名古屋市立大学医学部卒業。
合同会社ホワイトメディカルコンサルティング 代表社員。
医療鑑定・医療コンサルティング会社である合同会社ホワイトメディカルコンサルティングを運営して弁護士の医学的な業務をサポートしている。
【専門分野】
整形外科領域の画像診断、小児整形外科、下肢関節疾患