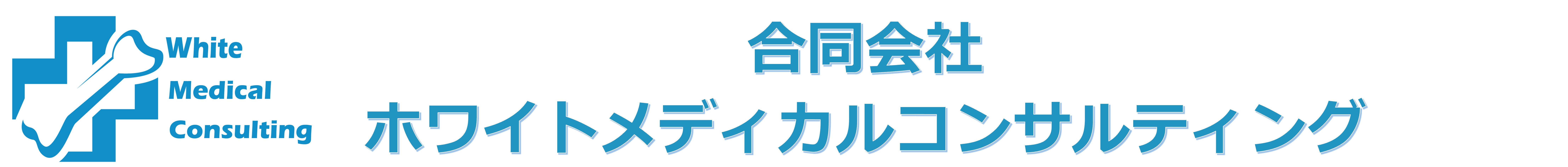事故によるむちうちの嘘がバレるリスクや嘘を疑われやすい理由

交通事故による「むちうち」は、目に見える外傷ではないため、そのつらい症状が保険会社や医師から「本当だろうか?」と疑いの目で見られてしまうことがあります。
安易な気持ちでむちうち症状を偽る「嘘」は、治療や調査の過程で必ずバレます。しかし、本当に苦しんでいる方まで、嘘だと誤解されてしまうケースも少なくありません。
そこでこの記事では、以下の内容を整形外科医が解説していきます。
- むちうちの嘘がバレたり疑われたりするケース
- むちうちの嘘がバレるリスク
- むちうちで本当に苦しむ方が正当な補償を受けるための正しい対応
また、記事の後半には、事故によるむちうちで適正な慰謝料を受け取るための方法についても解説しています。事故に遭われた方やむちうちの症状にお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。
※「むちうち」という言葉について
このコラムでは、皆様にとって馴染み深く、分かりやすい「むちうち」という言葉を使用して解説を進めますが、これは正式な病名ではなく、あくまで一般的な呼び名(俗語)です。
医療機関における正式な診断名は、「外傷性頚部症候群」となります。
1.そもそもむちうち(外傷性頚部症候群)とは?
むちうちとは、交通事故などによる頚部への外力により、頚椎領域の軟部組織損傷が発症することにより症状を呈する病態です。むちうちでは、レントゲンなどの画像に異常が描出されず、外傷の受傷歴や本人の訴える症状や臨床所見を頼りとして診断が下されるのが特徴です。
正式な傷病名としては「外傷性頚部症候群」などと呼ばれます。
この「客観的な画像所見により描出されにくい」というむちうちの病態の特徴が、時に嘘を疑われる原因にもなります。
1-1.むちうちの症状
むちうちの症状は、首の痛みや肩こりだけでなく、以下のような症状が出ることもあり、非常に多岐にわたります。
- 頭痛
- めまい
- 四肢のしびれ
交通事故による外力で、頚椎の筋群、椎間板、椎間関節、後根神経節、椎骨動脈、交感神経系などに傷害が引き起こされうるため、これの多彩な症状が発生するとされています。また、事故の直後ではなく、数時間から数日経ってから症状が出てくることも、むちうちの大きな特徴です。
この症状の多様性が、他人からは辛さを理解されにくい一因ともなっています。
関連記事:むちうちの症状が日によって違う理由とは?後遺障害認定への影響も解説
2.事故によるむちうち(外傷性頚部症候群)の嘘はバレる!

結論、慰謝料などを目的にむちうちの症状を偽ったり、症状を過大に申告したりする嘘は、保険会社や医師による客観的な調査や診察によって高確率でバレます。
保険会社も医師も、数多くの交通事故案件を扱ってきたプロです。彼らは、治療状況や言動に潜む不自然な点を見抜けるほどの専門的な知識や視点を持っています。
そのため症状がないのにむちうちだと嘘をつくのは、かえってご自身の立場を危うくするだけだと認識すべきです。
2-1.事故によるむちうちの嘘がバレたり疑われたりするケース
むちうちの嘘が疑われるのは、主に、患者様の訴えと、客観的な事実との間に、医学的・論理的な矛盾が見られる以下のようなケースです。
- 痛みの訴えが大げさで医学的な説明と一致しないケース
- 通院頻度や間隔が治療目的として不自然ケース
- 症状の訴えに一貫性がないケース
- 医師の治療方針に従わず特定の要求に固執するケース
- 事故から期間が経過して初めて強い症状を訴え始めるケース
保険会社は、通院記録や医師の所見、事故の状況などを照らし合わせ、その主張に一貫性や妥当性があるかを慎重に判断しています。これから紹介するような典型的なパターンに当てはまると、不正請求の可能性を疑われることになります。
2-1-1.痛みの訴えが大げさで医学的な説明と一致しないケース
痛みの訴えが、客観的な検査結果や、医学的な観点から見て、明らかに過剰または不自然である場合、その信憑性が疑われます。
たとえば、医師がおこなう神経学的検査(ハンマーで手足を叩く反射の検査など)で正常な反応しか出ていないにもかかわらず、「全く動かせないほどの激痛としびれがある」と訴え続けるようなケースです。
申告する症状と、医師による客観的な所見(他覚的所見)との間に大きな乖離があると、嘘を疑われる原因となります。
2-1-2.通院頻度や間隔が治療目的として不自然なケース
治療のためではなく、慰謝料の計算に有利になるように、通院頻度や期間を意図的に調整していると見なされると、むちうちが嘘ではないかと疑われます。
主に、症状が最も重いはずの事故直後の通院が少なく数カ月経ってから急に通院回数を増やしたり、痛みを訴えながらも仕事などを理由に月に1〜2回程度しか通院しなかったりするケースです。
むちうち治療の必要性に基づいた、医学的に妥当な通院ペースでないと、その一貫性のなさを指摘されます。
2-1-3.症状の訴えに一貫性がないケース
診察のたびに痛みを主張する場所が変わったり、症状の説明が毎回異なったりと、訴える内容に一貫性がない場合も、嘘を疑われる原因です。
もちろん症状には波がありますが、「前回は右腕がしびれると言っていたのに、今回は左足が痛い」というように、症状の関連性が医学的に説明できない場合、むちうちに対する信頼性は低くなります。
医師は、カルテに過去の訴えを全て記録しています。そのため、その場しのぎの嘘は、簡単に見破られてしまうのです。
2-1-4.医師の治療方針に従わず特定の要求に固執するケース
医師が「症状改善のためにはリハビリが必要」と提案しているにもかかわらず、それを拒否し、「とにかく湿布と痛み止めだけ出してほしい」といった特定の要求に固執するケースも、症状に対する疑念を抱かせます。
これは、症状を治すことよりも、通院日数や慰謝料だけが目的であるかのような印象を与えるためです。また、医師の治療方針に従わないことで症状が長引いていると判断され、治療の打ち切りを検討される原因にもなります。
2-1-5.事故から期間が経過して初めて強い症状を訴え始めるケース
事故から、数週間や1カ月以上といった相当な期間が経過してから初めて医療機関を受診し、「事故が原因で首が痛い」と訴えるケースです。
この場合、その症状が本当に事故によるものなのか、あるいは事故とは無関係な、別の原因で発生したのか、その因果関係を証明するのが極めて困難になります。
保険会社からは、事故との関連性を否定され、治療費などの支払いを拒否される可能性が高くなるでしょう。
2-2.事故によるむちうちの嘘がバレる相手
むちうちの嘘は、特定の誰か一人にバレるというわけではなく、「保険会社の担当者」「医師」「調査員」といった複数の視点から多角的に見破られます。
まず、保険会社の担当者が、提出された書類や通院状況に矛盾がないかを精査します。
次に、医師が、患者の訴えと、神経学的検査などの客観的な所見とが一致するかを、医学的な観点から判断します。
そして、とくに疑わしいケースでは、保険会社から依頼された調査員が日常生活の行動を調査することもあります。
このように、金銭、医療、事実関係というそれぞれの専門家によるチェックの網を、一つの嘘で通り抜けるのは極めて困難なのです。
3.事故によるむちうち(外傷性頚部症候群)が嘘であるとバレるリスク
事故によるむちうちの症状を偽る嘘が発覚した場合、以下のようなリスクが生じます。
- 刑事罰のリスク
- 金銭的なリスク
- 社会的信用を失うリスク
軽い気持ちでついた嘘が、その後の人生を大きく狂わせる可能性があることをよく理解しておく必要があります。詳しく見ていきましょう。
3-1.刑事罰のリスク
嘘の申告で保険金や慰謝料を不正に受け取ろうとする行為は、刑法の「詐欺罪」にあたり、刑事罰の対象となる可能性があります。そのため、保険会社が悪質だと判断し警察に被害届を提出すれば、捜査の対象となるのです。
もし有罪判決となれば、10年以下の懲役という重い刑罰が科されることもあります。その後の人生に「前科」という、取り返しのつかない記録が残ってしまうのです。
3-2.金銭的なリスク
嘘が発覚した場合、当然ながら、慰謝料などの保険金は一切支払われないうえ、すでに受け取った金銭の返還を求められるという金銭的なリスクが生じます。
まず保険会社からは、それまでに病院に対して支払われた治療費の全額について、一括での返金を求められることになります。また、悪質なケースでは、調査にかかった費用(探偵や調査会社の費用)まで損害賠償として請求されることもあります。
お金を得るどころか、結果として、数百万円単位の借金を背負うことになりかねません。
3-3.社会的信用を失うリスク
もし詐欺罪で有罪となれば、その事実は職場や家族に知られることになり、社会的信用を失うリスクがあります。
また、前科があることで、その後の再就職や、ローンを組む、特定の資格を取得するといった人生の様々な場面において、計り知れない不利益を被り続けます。
一度の過ちが、その後の人生におけるあらゆるチャンスを奪ってしまう可能性があるのです。
4.事故によるむちうち(外傷性頚部症候群)が嘘だと疑われやすい4つの理由
事故によるむちうちが嘘だと疑われやすい理由として、主に以下の4つが挙げられます。
- 医学的な所見が見られないことが多いから
- 事故直後ではなくあとから症状が出ることが多いから
- 症状が多様で一貫性がないように見えるから
- 事故の大きさと治療期間が比例しないことが多いから
詳しく解説します。
4-1.医学的な所見が見られないことが多いから
むちうちが疑われやすい最大の理由は、むちうち自体がレントゲンやCTといった画像検査では異常が見つからない、つまり客観的な医学的所見に乏しいからです。
むちうちの損傷の多くは、骨ではなく、筋肉や靭帯といった軟部組織に起こります。そのため、診断は本人の「痛い」「しびれる」といった自覚症状の訴えに、大きく依存せざるを得ません。
客観的証拠の乏しさが、むちうちに対して「本当に痛いのか?」という疑念を招く根本的な原因となっています。
4-2.事故直後ではなくあとから症状が出ることが多いから
事故直後には痛みがなく、数時間後や翌日になってから症状が現れるという、むちうち特有の「遅発性」も、むちうちが嘘だと疑われやすい理由です。
事故直後は、心身が興奮状態にあり、痛みを感じにくくなっています。しかし第三者から見ると、「事故の時は平気だったのになぜ今頃痛むのか」と、事故と症状との因果関係を疑わしく感じさせてしまいます。
事故から症状発症までの時間差が、症状の正当性を主張するうえで一つのハードルとなることがあります。
関連記事:むちうちの症状が出るまでの期間は?遅れて出る理由と早期対応の重要性
4-3.症状が多様で一貫性がないように見えるから
むちうちの症状は、首の痛み以外にも、頭痛、めまい、耳鳴り、四肢のしびれなど非常に多様で、日によって強さも変動します。そのため、痛みの訴えに一貫性がないように見られがちです。これは、事故によって自律神経系にも影響を及ぼすために起こる、むちうちの特徴に関係しています。
主張する症状に一貫性が見られないと、事情を知らない第三者から「昨日と言っていることが違う」「症状が多すぎて、本当とは思えない」といった、不信感に繋がってしまう場合があります。
4-4.事故の大きさと治療期間が比例しないことが多いから
車の損傷がほとんどないような軽微な物損事故であるにもかかわらず、治療が半年、1年と長期化する場合も、症状の妥当性を疑われる原因となります。
もちろん、事故の規模とむちうち症状の重さが必ずしも比例するわけではありません。停車中の追突などの無意識下の外傷では軽微な外力でもむちうちは発症しやすいとされています。しかし、保険会社などは、まず事故の客観的な状況から症状の度合いをある程度推測します。
その推測と、実際の治療期間との間に大きなギャップがあると、「治療を不当に引き延ばしているのではないか」という疑念を招きやすくなるのです。
5.事故によるむちうち(外傷性頚部症候群)を嘘だと誤解されないためにできること7選
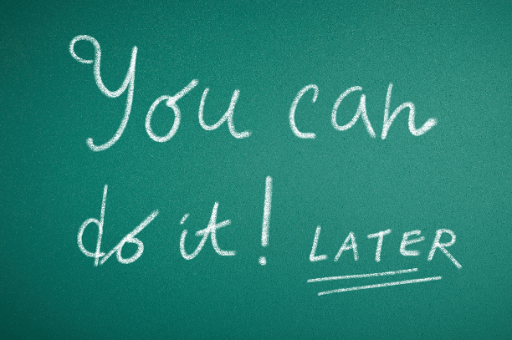
本当に症状で苦しんでいるにもかかわらず、「嘘ではないか」と疑われるのは非常につらいことです。そこで、事故によるむちうちを嘘だと誤解されないためにできることを、以下の7つに分けて解説していきます。
- 事故後すぐ整形外科を受診する
- 医師の指示に従い通院を継続する
- 症状は具体的かつ一貫して伝達する
- MRIやレントゲンなど精密検査で証拠を残す
- 日常生活での支障も記録する
- ドライブレコーダーのデータを提出する
- 弁護士に相談する
それぞれ確認してください。
5-1.事故後すぐ整形外科を受診する
事故に遭ったら、たとえその場では痛みがなくても、必ず当日中、遅くとも数日以内に整形外科を受診してください。これは、事故とむちうち症状との「因果関係」を証明するための最も重要な初動です。
事故から初診までの期間が空いてしまうと、「その症状は事故とは無関係では?」と疑われる最大の原因となります。整骨院や接骨院ではなく、医師による診断書が発行される「整形外科」を受診することが鉄則です。
5-2.医師の指示に従い通院を継続する
痛みが続く限り、医師の指示に従って、真面目に、そして継続的に通院を続けることが、むちうち症状の存在を証明するために不可欠です。通院の頻度や期間は、むちうち症状がそれだけ重く、治療が必要であることを示す客観的な証拠となります。
自己判断で通院を中断したり、通院間隔が不規則だったりすると、「もう治ったのでは?」と判断され、治療費の打ち切りなどを打診される原因になります。むちうちの痛みの波に左右されず、一貫した治療を続ける姿勢が大切です。
5-3.症状は具体的かつ一貫して伝達する
診察時には、頚部痛などのむちうちの自覚症状を、できる限り具体的かつ一貫性をもって医師に伝えるよう心がけましょう。
「いつ、どこが、どんな風に痛むのか」「常時痛みがあるのか」などを詳しく伝えると、医師はカルテに詳細な記録を残せます。カルテに記載されている情報が、のちの後遺障害認定などでも重要な証拠となります。
診察のたびにむちうち症状に関する訴えが変わると信憑性が疑われるため、一貫した説明をするようにしてください。
関連記事:【むちうちの症状の伝え方】重要性やポイント・注意点
5-4.MRIやレントゲンなど精密検査で証拠を残す
レントゲンで「異常なし」と診断されてもむちうちの痛みやしびれが続く場合は、医師に相談のうえ、MRIなどの精密検査を受けることを検討しましょう。
レントゲンは骨の異常しか分かりませんが、MRIであれば、「神経の圧迫」や「筋肉・靭帯といった軟部組織の損傷」を画像として捉えられる可能性があります。
このような客観的な医学的所見(他覚的所見)は、あなたの症状が嘘ではないことを証明する、非常に強力な証拠となるのです。
5-5.日常生活での支障も記録する
むちうちの症状によって、日常生活を送るうえで「できなくなったこと」や、「支障が出ていること」を、簡単なメモでも良いので記録しておきましょう。
「痛みのせいで長時間座って仕事を続けられない」「首が回らず車の運転で安全確認がしにくい」といった具体的な記録は、むちうちの症状が現実の生活にどれだけ影響を及ぼしているかを示す、説得力のある証拠となります。
この記録を医師や弁護士に伝えることで、症状の深刻さをより正確に理解してもらえます。
5-6.ドライブレコーダーのデータを提出する
もしご自身の車にドライブレコーダーが設置されていれば、その録画データを、事故状況を証明する客観的な証拠として提出しましょう。映像によっては、事故時の衝撃の大きさや相手方との過失割合などを客観的に証明できます。
とくに、相手方が「軽くぶつかっただけだ」と主張しているような場合に、事故の激しさを示す強力な反論材料です。事故の規模が大きかったことを証明できれば、むちうち症状の深刻さに対する主張の説得力も増します。
5-7.弁護士に相談する
保険会社の対応に少しでも疑問や不満を感じたり、症状が長引いて後遺障害の認定を考えたりする段階になったら、交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。
弁護士は、あなたの代理人として、法的な観点から保険会社と対等に交渉してくれます。また、後遺障害認定の手続きをサポートし、あなたの症状に見合った、最も高い基準での慰謝料を請求してくれます。
法律の専門家を味方につけることが、あなたの正当な権利を守り最善の結果を得るための最も確実な方法です。
6.事故によるむちうち(外傷性頚部症候群)が嘘だと決めつけられたときの対処法
もし相手方の保険会社から、むちうちの症状が嘘だと決めつけられ、治療費の支払いを一方的に打ち切られたとしても、決して諦める必要はありません。保険会社の判断が、必ずしも医学的・法的に正しいとは限らないからです。
事故によるむちうちが嘘だと決めつけられたときは、以下の対処法を実践してください。
- 医師と相談しながら治療を継続する
- 健康保険や自賠責で治療を継続する
- 保険会社と交渉する
一つずつ解説します。
6-1.医師と相談しながら治療を継続する
たとえ保険会社から治療費の打ち切りを告げられても、医師が「まだ治療が必要だ」と判断している限り、自己判断で通院をやめてはいけません。治療を中断してしまうと、「もう治ったのですね」と相手方の保険会社の主張を認めたことになりかねないためです。
痛みやしびれといった症状が残っている限り、医師と相談しながら、治療を継続する意思を明確に示すことが非常に重要です。治療の継続こそが、むちうち症状が本物であることの何よりの証拠となります。
6-2.健康保険や自賠責で治療を継続する
任意保険会社からの支払いが止まった場合は、ご自身の健康保険を使って治療を継続してください。また、相手方の自賠責保険に対して、治療費などを直接請求する「被害者請求」という方法もあります。
このように、むちうちの治療を継続するための方法は確保されています。まずは治療を最優先し、費用の問題は、その後の示談交渉や弁護士への相談を通じて解決を目指しましょう。
6-3.保険会社と交渉する
治療費の支払いを再開してもらう、あるいは最終的な示談交渉において、正当な賠償額を認めてもらうために保険会社と交渉をおこないます。このとき、感情的に反論するのではなく、これまでのカルテ記録やMRIなど客観的な検査結果をもとに、「医学的な必要性」を主張することが重要です。
ただし、個人が専門知識を持つ保険会社の担当者と対等に交渉するのは非常に困難かつ、精神的な負担も大きいため、弁護士に代理を依頼するのが最も賢明な選択です。
7.事故によるむちうち(外傷性頚部症候群)で適正な慰謝料を受け取るための方法
事故によるむちうちで受けた精神的・肉体的な苦痛に見合った慰謝料を受け取るためには、事故直後から、証拠を意識した正しい行動を積み重ねていく必要があります。主に以下の4点を実践してみてください。
- 事故後すぐに通院を開始する
- 通院を継続する
- 勤務先に休業損害証明書を作ってもらう
- 後遺障害等級認定を申請する
それぞれ解説します。
7-1.事故後すぐに通院を開始する
事故に遭ったら、むちうちの自覚症状の有無や程度にかかわらず、事故後すぐに整形外科を受診し治療を受けましょう。
事故日と初診日が離れていると、保険会社から、症状と事故との因果関係を疑われてしまいます。痛みがあとから出てきた場合でも、事故との関連性を明確にするためなるべく速やかな受診が不可欠です。
7-2.通院を継続する
医師が治療の必要性を認めている間は、指示された頻度で継続的に通院することが重要です。
通院実績は、むちうち症状が治癒せず、治療を要する状態であったことを示す客観的な証拠となります。通院間隔が不規則な場合、症状の程度が軽いと見なされ、入通院慰謝料が低く計算される原因にもなります。
むちうち症状の回復のためだけでなく、正当な慰謝料を受け取るためにも、真面目に通院を継続するようにしてください。
関連記事:むちうちの治療期間はどの程度?治療期間が慰謝料に与える影響を解説
7-3.勤務先に休業損害証明書を作ってもらう
むちうちの症状が原因で仕事を休んだり、遅刻・早退したりした場合は、その事実を証明するために勤務先に「休業損害証明書」を作成してもらいましょう。この書類をもとに、仕事を休んだことで得られなかった収入(休業損害)を、相手方の保険会社に請求できます。
パートやアルバイトの方でも、事故がなければ得られたはずの収入を請求する権利があります。事故による経済的な損失を、きちんと補償してもらうための重要な手続きです。
7-4.後遺障害等級認定を申請する
6カ月以上治療を続けても、痛みやしびれといった症状が改善しない場合は、後遺障害等級認定の申請を検討してください。
むちうちが後遺障害に認定されると、治療期間に対する慰謝料とは別に、「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」という高額な賠償金を請求できるようになります。
(逸失利益とは、本来得られたはずの収入や利益が事故や損害により得られなくなったことによって生じる経済的損失のこと)
7-4-1.後遺障害等級認定の申請方法
後遺障害等級認定の申請方法には、相手方の任意保険会社に手続きを任せる「事前認定」と、被害者側で書類を集めて申請する「被害者請求」の2種類があります。
手間が少ないのは事前認定ですが、保険会社に不利な証拠は提出されない可能性があります。
一方、被害者請求は手間がかかりますが、こちらに有利な医学的証拠を追加で提出できるため、より適正な等級認定を目指せるという点が大きなメリットです。弁護士に依頼する場合は、被害者請求の方法を選択します。
関連記事:後遺障害の事前認定とは?メリット・デメリットや異議申し立ての方法
8.まとめ
この記事では、むちうちの嘘がバレる仕組みと、その先に待つ大きなリスク、そして本当に症状で苦しむ方が嘘だと誤解されずに正当な補償を受けるための方法を解説しました。
結論として、むちうちの症状について安易に嘘をつくことは、刑事罰や多額の賠償請求という、人生を揺るがす代償に繋がります。
一方で、むちうちで本当に苦しんでいる方がすべきことは、医師の指示に従って一貫した治療を続け、その事実を客観的な記録として積み重ねていくことです。
あなたの主張を正しく証明するため、そして不当な疑いから身を守るため、少しでも不安があれば、迷わず弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。
合同会社ホワイトメディカルコンサルティングでは、むちうちの後遺障害認定に有効な証拠となる医学意見書の作成をおこなっております。
むちうちの症状を抱え医学意見書が必要な状況にある方は、是非弊社にご依頼ください。
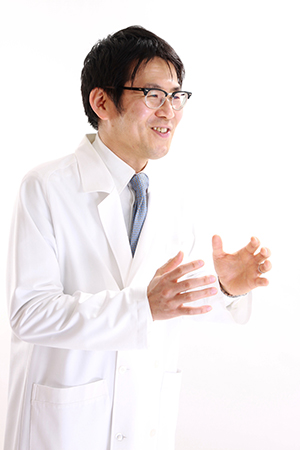
このコラムの著者
白井 康裕
【経歴・資格】
・日本専門医機構認定 整形外科専門医
・日本職業災害医学会認定 労災補償指導医
・日本リハビリテーション医学会 認定臨床医
・身体障害者福祉法 指定医
・医学博士
・日本整形外科学会 認定リウマチ医
・日本整形外科学会 認定スポーツ医
2005年 名古屋市立大学医学部卒業。
合同会社ホワイトメディカルコンサルティング 代表社員。
医療鑑定・医療コンサルティング会社である合同会社ホワイトメディカルコンサルティングを運営して弁護士の医学的な業務をサポートしている。
【専門分野】
整形外科領域の画像診断、小児整形外科、下肢関節疾患