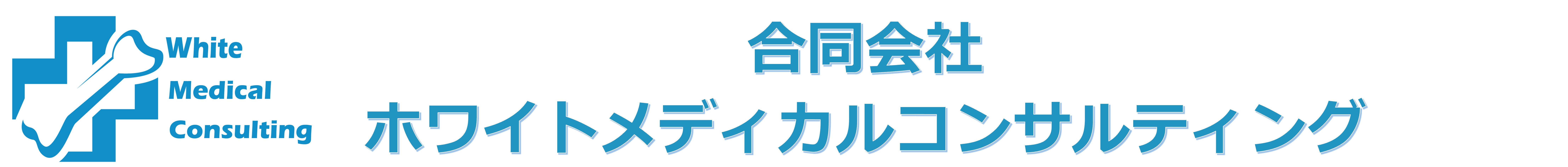むちうちはレントゲンでわかる?「異常なし」といわれたときの対処法
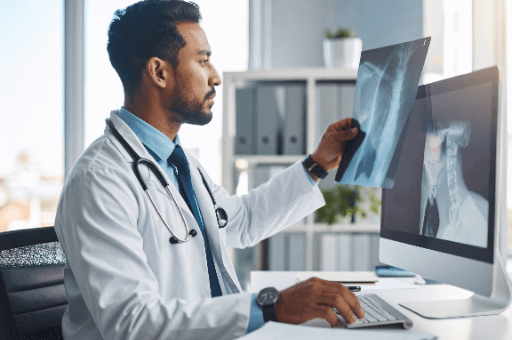
「交通事故にあったあと、首の痛みがつらかったため病院に行ったところ、レントゲンで骨に異常なしと言われた」
「痛みは確かにあるのに異常が見つからず、このままでは十分な治療や補償を受けられないのではないか」
そのようなご不安を抱えていませんか?
実は、むちうちの痛みの多くは、レントゲンには写らない筋肉や神経の損傷が原因です。「異常なし」という言葉を鵜呑みにし、適切な対応を怠ると、あとで正当な後遺障害の認定を受けられなくなる可能性もあります。
そこでこの記事では、整形外科医が主に以下の内容を解説しています。
- むちうちとレントゲンの関係
- むちうちをレントゲン検査する際の注意点
- むちうちのレントゲンで異常なしと言われたら?
むちうちはレントゲンでわかるのか、どのような関係があるのか気になる方は、ぜひ最後までご覧ください。
※「むちうち」という言葉について
このコラムでは、皆様にとって馴染み深く、分かりやすい「むちうち」という言葉を使用して解説を進めますが、これは正式な病名ではなく、あくまで一般的な呼び名(俗語)です。
医療機関における正式な診断名は、「外傷性頚部症候群」となります。
1.むちうち(外傷性頚部症候群)はレントゲン検査でわからないことがある
むちうちは、レントゲン検査では異常が見つからないケースが多いです。なぜなら、レントゲン検査は骨の異常を写すことに長けているのですが、むちうちの主な原因である首周りの筋肉や靭帯(じんたい)といった軟部組織の損傷は写らないためです。
そのため、頚部痛などのむちうちの症状があっても、レントゲン検査画像では「異常なし」と診断される場合が少なくありません。痛みの原因を特定するには、ほかの検査や問診が重要になります。
1-1.むちうちとは?
そもそもむちうちとは、交通事故などの衝撃による頚部への外傷により頚部が前屈・後屈を強制され、軟部組織損傷をもたらすことにより症状を発症する病態です。
とくに無意識下の追突事故の際には軽微な外力でも起こりやすいとされ、多岐にわたる症状を引き起こすのが特徴です。
1-2.むちうちの症状
むちうち(外傷性頚部症候群)の症状としてイメージしやすいのが首の痛みですが、実際にはそれ以外にもさまざまな症状が出ます。首そのものの痛みの他にも、肩の痛み、頭痛、四肢のしびれ、めまい、耳鳴りなど首以外の場所にも症状が現れる場合があります。
事故の直後は興奮しているため症状を感じにくく、数時間後から翌日にかけて痛みが出てくるのも珍しくありません。
関連記事:むちうちの症状が出るまでの期間は?遅れて出る理由と早期対応の重要性
1-3.なぜむちうちの診断でレントゲンを撮るのか
ではなぜ、むちうちの診断でレントゲンを撮るのでしょうか。むちうちの診断でレントゲンを撮る一番の理由は、骨折や脱臼といった、より重症で危険なケガがないかを確認するためです。
むちうちによる軟部組織の損傷はレントゲンに写りませんが、首の骨に異常があれば大変な事態に繋がる可能性があります。まずは命に関わるような重大な損傷がないかを確かめるのが、安全に治療を進める上で非常に重要になるのです。
2.レントゲン検査でわかるむちうち(外傷性頚部症候群)の所見
レントゲン検査では、むちうちの直接的な原因は写らないものの、診断の参考になる間接的な所見が見つかる場合があります。
具体的には、事故の衝撃による骨折や脱臼の有無、首の骨の並び方の変化(ストレートネック)、そして事故の前から存在していた可能性のある首の骨の加齢性変性などです。
これらの情報をもとに、総合的に首の状態を判断していきます。
2-1.骨折や脱臼
骨折や脱臼は、レントゲン検査で最も明確にわかる所見です。
交通事故のような強い衝撃が加わると、首の骨(頚椎)が折れたり、ずれたりする危険性があります。これらは神経に重大な損傷を与えかねない危険な状態のため、まず確認すべき最優先事項です。
もし骨折や脱臼が見つかった場合は、むちうちとは異なる専門的な治療が緊急で必要となります。
2-2.ストレートネック

首の骨は側面からみると正常では前方に凸の緩やかなカーブを持っています。ストレートネックは、本来あるはずの首の骨の前方に凸の緩やかなカーブが消失して、あたかも首の骨がまっすぐに配列しているように見える状態です。
過去にはストレートネックはむちうちによる首の周りの筋肉の緊張を反映しているとされていましたが、今では健常人でも同様にストレートネックがみられることから、レントゲン検査におけるストレートネックは病的な意義は無いという医学的意見が多くなっています。
2-3.変性所見
変性所見とは、主に加齢にともなう首の骨の変化のことで、レントゲンで確認が可能です。たとえば、骨のトゲ(骨棘)や、骨と骨の間が狭くなっている状態(椎間腔の狭小化)などがこれにあたります。
変性所見は、事故が原因で生じたものではありませんが、もともとあった変性所見をもとに、事故の外力によって痛みなどの症状が出現している可能性があります。症状の原因を考えるうえでの参考情報となります。
3.むちうち(外傷性頚部症候群)をレントゲン検査する際の注意点
むちうちでレントゲン検査を受ける際は、その結果が全てではないと理解しておくことが重要です。
レントゲン検査は骨の異常を見るためのもので、痛みやしびれの原因である軟部組織の損傷は写りません。そのため、「異常なし」という結果に安心したり、逆に不安になったりせず、医師の総合的な診断を仰ぐ必要があります。
また、むちうちの所見があった場合も、それが法的にどう評価されるかを知っておくことが大切です。
3-1.レントゲン検査では異常なしとなることが多い
前述したように、むちうちはレントゲン検査で異常なしとなることが多いです。レントゲン検査は骨の状態を写す検査であり、むちうちの痛みの主原因である筋肉や靭帯、神経などの軟部組織損傷を捉えるのができないからです。
万が一むちうちの自覚症状がある場合は、レントゲン検査で異常なしといわれても、我慢せず医師にしっかりと症状を伝え続けることが重要となります。
3-2.ストレートネックでは後遺障害が認められにくい
レントゲンでストレートネックと診断されても、それだけを理由に後遺障害が認定されるのは難しいのが現状なのです。前述した通り、ストレートネックは健常人でも起こりうるため、病的意義は少ないと考えられているためです。
後遺障害の認定には、MRI画像での神経圧迫など、より客観的で異常を示す医学的証拠が求められます。
4.むちうち(外傷性頚部症候群)のレントゲン検査で異常なしと言われたら?
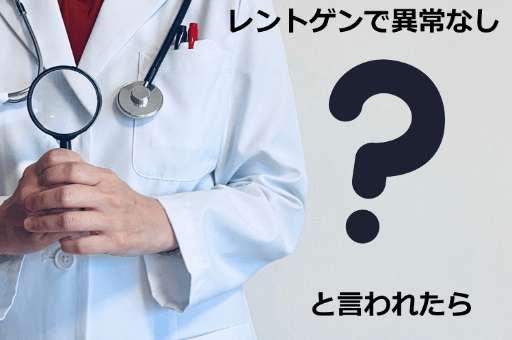
レントゲン検査で異常なしと診断されても、痛みやしびれなどの症状が続く場合は、より詳しい精密検査を検討しましょう。
レントゲンは、あくまで骨の異常を確認する初期検査にすぎません。症状の本当の原因を突き止めるためには、神経など軟部組織の状態を詳しく見られるMRI検査など、別の角度からのアプローチが必要になります。
4-1.MRIによる検査がおすすめ
むちうちの精密検査として、とくに推奨されるのがMRI検査です。その理由は、以下の3つです。
- レントゲンではわからない「軟部組織の状態」を可視化できるため
- むちうちの正当な補償に繋げるため
- より的確な治療方針を立て回復を早めるため
詳しく解説します。
4-1-1.レントゲンではわからない「軟部組織の異常」を可視化できるため
MRI検査はレントゲンではわからない痛みに関して、「軟部組織の異常」を画像として可視化できるからです。
MRI検査は、レントゲンには写らない椎間板や神経といった軟部組織の状態を、3次元で鮮明に映し出すことができます。たとえば、脊髄や神経を圧迫している椎間板ヘルニアや脊髄症や神経根症といった異常所見を明確に捉えることが可能です。
原因が目に見える形で特定できると、今後の治療や補償の手続きに大きく役立ちます。
4-1-2.むちうちの正当な補償に繋げるため
むちうちで正当な補償を受けるためには、MRI検査による客観的な証拠が非常に重要です。
「痛い」「しびれる」といった本人の訴えだけでは、むちうちの症状を証明するのが難しい場合があります。MRI検査で異常所見が画像として示されれば、症状の存在を医学的に証明でき、後遺障害の認定や慰謝料請求などを有利に進められるでしょう。
4-1-3.より的確な治療方針を立て回復を早めるため
MRI検査で症状の原因を正確に特定できると、より的確な治療方針を立てられ、結果として早期回復に繋がります。
たとえば、頚椎椎間板ヘルニアによる脊髄や神経根の圧迫がMRI検査でわかれば、それに合わせたリハビリテーションや薬の処方が可能です。やみくもな治療ではなく、むちうちの原因に直接アプローチする治療をおこなえるのが、早期の社会復帰を目指すうえで大きな利点です。
4-2.むちうちに対するMRI検査以外の精密検査
むちうちの精密検査には、MRI検査以外にも「CT検査」および「神経学的検査」があります。それぞれ得意な分野が異なるため、症状に応じて医師が最適な検査を選択する必要があります。
それぞれの検査について、詳しく見ていきましょう。
4-2-1.CT検査:レントゲンでは見えない微細な骨折を発見する
CT検査は、レントゲンでは見逃してしまうような、ごく小さな骨折(微細骨折)の発見に優れています。体を輪切りにするように撮影し、コンピューターで立体的な画像を再構成するため、レントゲンよりもはるかに詳しく骨の状態を観察できるためです。
とくに、複雑な形状の頚椎の骨折などを調べる際に非常に有用な検査です。
4-2-2.神経学的検査:医師がおこなう身体的なテストで異常を見つける
神経学的検査は、医師が打腱器などの器械を使っておこなう身体的なテストで、神経の働きに異常がないかを調べます。
具体的には、腱反射は正常か、筋力がしっかり入るかなどをチェックします。画像検査では異常が見つからなくても、この検査で異常が認められれば、神経症状の客観的な証拠となり得ます。
5.「レントゲン検査で異常なし」は慰謝料請求で不利になる?
むちうちの症状を負った方が気になるのが、「レントゲン検査で異常なし」となった際に慰謝料請求で不利になるのかという点ではないでしょうか。
ここでは、レントゲンで異常なしとなった際に慰謝料請求はどうなるのか、解説します。
5-1.不利になるとは限らない
レントゲン検査で骨に異常が見つからなくても、首の痛みなどの自覚症状があり、医師がむちうちと診断して治療が必要だと判断すれば、通院に対する慰謝料(入通院慰謝料)は請求できます。
大切なのは、自己判断で通院をやめず、医師の指示に従って適切な頻度で治療を続けることです。通院の実績が、ケガの存在と治療の必要性を示す証拠となります。
関連記事:【むちうちの症状の伝え方】重要性やポイント・注意点
5-2.慰謝料の金額が低くなる可能性はある
一方で、慰謝料の算定基準では、レントゲンで客観的な異常所見(他覚症状)が見られる場合に比べ、痛みなどの自覚症状しかない場合は金額が低くなる傾向があります。これは、ケガの程度を客観的に証明することが難しいためです。
5-3. 「後遺障害慰謝料」の認定は難しくなる
治療を続けても症状が残ってしまった場合に請求する「後遺障害慰謝料」については、「レントゲン検査で異常なし」だと認定のハードルが非常に高くなります。
後遺障害として認定されるには、症状が残っていることを医学的に証明する必要があるため、MRI検査で脊髄や神経根の圧迫が見られるなどの客観的な証拠が重要になります。
5-4.MRI検査で異常が見つかれば後遺障害等級認定で有利になる可能性がある
レントゲン検査以外のMRI検査などの精密検査で異常所見が見つかると、後遺障害等級の認定において有利に働く可能性があります。
後遺障害の認定には、症状の原因を客観的に示す医学的な証拠が求められます。MRI検査で脊髄や神経の圧迫などが確認できれば、訴えているむちうちの症状と画像所見が一致するため、後遺障害14級や12級といった等級が認定される確率が格段に高まります。
関連記事:後遺障害14級の認定を受けるデメリットはある?認定のポイントも解説
6.【弁護士の先生へ】むちうち(外傷性頚部症候群)の後遺障害認定は弊社にお任せください
むちうち(外傷性頚部症候群)の後遺障害等級認定において、「レントゲンで異常なし」とされたクライアントの立証にお困りではございませんか?
適切な後遺障害等級認定を勝ち取るためには、症状と事故との因果関係を明確にする、客観的な医学的証拠が不可欠です。
弊社は、交通事故案件を専門とする医療鑑定・医療コンサルティング会社です。先生方が不得手とされる医学的分野の立証活動を、私たちが全面的にサポートいたします。
これまでの豊富な経験に基づき、後遺障害診断に有効な検査(MRI検査など)のアドバイスから、カルテや後遺障害診断書の精査、医学意見書の作成まで、ワンストップで対応します。先生方が法的主張に専念できるよう、強力な医学的根拠をご提供し、クライアントの正当な権利獲得に貢献します。
むちうちの案件でお悩みの弁護士の方は、ぜひ弊社までご相談ください。
※弊社は弁護士の先生からのお問い合わせに対してのみ、サービスを承っております。そのため事故の被害にあった当事者の方は、必ず代理人弁護士の先生を通してご連絡頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。
関連ページ:交通事故や医療過誤等の医学意見書作成
7.まとめ
むちうちは、レントゲン検査ではわからないケースが多い症状です。レントゲン検査で「異常なし」といわれても、あなたが抱える痛みなどの症状が気のせいだということでは決してありません。むしろ、それは骨以外の軟部組織の異常による可能性があり、より詳しい検査へ進むべきだという重要な手がかりです。
とくに後遺障害が残ってしまった場合、MRI検査などの客観的な医学的証拠がなければ、正当な後遺障害等級の認定を受けるのは非常に困難になります。
適切な検査や治療、そして補償について少しでも不安があれば、一人で悩まず、交通事故問題に精通した弁護士へご相談ください。
合同会社ホワイトメディカルコンサルティングでは、むちうちの後遺障害認定に有効な証拠となる医学意見書の作成をおこなっております。
むちうちの症状を抱え医学意見書が必要な状況にある方は、ぜひ弊社にご依頼ください。
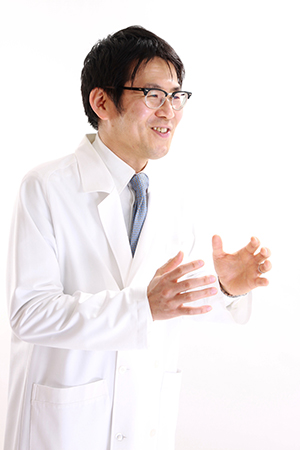
このコラムの著者
白井 康裕
【経歴・資格】
・日本専門医機構認定 整形外科専門医
・日本職業災害医学会認定 労災補償指導医
・日本リハビリテーション医学会 認定臨床医
・身体障害者福祉法 指定医
・医学博士
・日本整形外科学会 認定リウマチ医
・日本整形外科学会 認定スポーツ医
2005年 名古屋市立大学医学部卒業。
合同会社ホワイトメディカルコンサルティング 代表社員。
医療鑑定・医療コンサルティング会社である合同会社ホワイトメディカルコンサルティングを運営して弁護士の医学的な業務をサポートしている。
【専門分野】
整形外科領域の画像診断、小児整形外科、下肢関節疾患