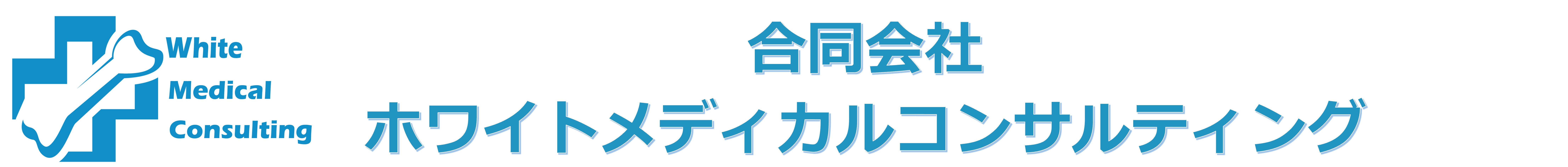しびれで後遺障害14級が認定されるためのポイント6選
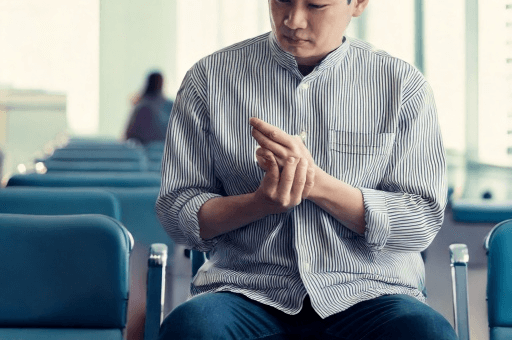
交通事故や仕事中の事故によって、上肢や下肢にしびれが残っているという方はいませんか?しびれの症状が続き、医師から症状固定と判断された場合は、後遺障害14級に認定される可能性があります。
そこでこの記事では、以下の内容について徹底解説していきます。
- 後遺障害として「しびれ」が残る傷病の例
- しびれで認定される後遺障害等級の種類
- しびれで後遺障害14級に認定されるためのポイント
この記事を読むことで、しびれによる後遺障害14級の概要から今後の対応について、理解を深められます。しびれによる後遺障害で悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。
1.後遺障害として「しびれ」が残る傷病の例
交通事故や労災などの影響で、手足や体の一部に「しびれ」が残ることがあります。このような神経症状は、後遺障害として認定される場合があります。具体的な傷病は、以下のようなものです。
- 外傷性頚部症候群(≒むち打ち≒頚椎捻挫≒頚部挫傷)
- 腰椎捻挫(≒頚部挫傷)
- 頚椎・腰椎椎間板ヘルニア
- 末梢神経損傷
- 脊髄損傷
これらの傷病により、日常生活に支障をきたす常時の「しびれ」が残存した場合、後遺障害等級の認定を受けることが可能です。
関連記事:労災によるしびれで認定される後遺障害等級や給付金額・認定のポイント
2.しびれで認定される後遺障害等級は2種類
しびれで認定される後遺障害等級は、以下の2種類です。
- 14級9号
- 12級13号
それぞれの内容を簡単に解説します。
2-1.14級9号
14級9号は、「局部に神経症状を残すもの」と定義されています。MRIやCTなどの画像検査や神経伝導速度検査や筋電図検査で明確な異常が確認できないものの、受傷からの経過や治療状況から、しびれが単なる故意の誇張ではないと推定され、かつ一貫して持続しており、しびれなどの自覚症状が医学的に説明可能な場合に認定される後遺障害等級です。
たとえば、外傷性頚部症候群(むち打ち)で画像上は異常が見られないが、しびれが常時持続・残存しているケースなどが該当します。
関連記事:後遺障害14級の認定を受けるデメリットはある?認定のポイントも解説
2-2.12級13号
12級13号は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」とされています。この等級は、MRIやCTなどの画像検査や神経伝導速度検査や筋電図検査などで医学的・他覚的にしびれ(≒神経症状)の存在が明確に確認できて、しびれが常時持続・残存している場合に該当します。
たとえば、椎間板ヘルニアで神経根の圧迫が画像上明らかであり、常時しびれが持続・残存しているケースがこれに該当します。
後遺障害等級の認定は、症状の程度や医学的証拠に基づいて判断されます。適切な等級認定を受けるためには、専門医の診断や詳細な検査結果の判断が重要となります。
3.しびれで後遺障害14級に認定されるためのポイント

しびれで後遺障害14級に認定されるためのポイントは、以下の6つです。
- しびれの症状と事故との因果関係がはっきりしている
- 医学的・他覚的な検査がしっかりされている
- 症状が持続するため一定の期間病院へ通院している
- 適度な頻度で通院を続ける
- 残存した症状の証明となる適切な書類を準備する
- 事前認定ではなく被害者請求をおこなう
後遺障害14級に認定されやすくなるためにも、一つずつ解説していきます。
3-1.しびれの症状と事故との因果関係がはっきりしている
事故後1週間や1ヵ月などの経過でしびれの症状が出現する場合は、事故後から症状が一貫して持続していないと判断され、残存したしびれと事故との因果関係がないと認定される可能性が高くなってしまいます。
寒いときや天気の悪いときだけしびれが出現するというケースも症状に一貫性がないと判断されるので気を付けましょう。
また、外傷性頚部症候群では外傷後6時間以内に65%、24時間以内に93%、72時間以内に100%の患者に症状が出現するという医学的な報告があります。そのため、事故後3日前後で症状が出現しており、病院に受診して入れば事故との因果関係がはっきりします。
3-2.医学的・他覚的な検査がしっかりされている
後遺障害14級の認定を受けるためには、医学的・他覚的な検査がしっかりおこなわれている必要があります。レントゲン、CTやMRIの画像検査の異常所見やスパーリングテストやジャクソンテストや腱反射などの神経学的異常所見などの他覚的所見が認められない場合、後遺障害等級が認定されない可能性が高くなるためです。
外傷性頚部症候群(むちうち)においては、画像検査や神経学的所見などの異常所見が認められないことが多いです。たとえ異常所見が無かったとしても、頚椎MRI検査などの精密検査を受けている場合は、しびれの症状が重かったと判断され、後遺障害の認定がされやすくなる可能性があると推測されます。
症状が持続する場合は、その原因を詳しく調べることが重要です。そのため、できるだけ早い段階でレントゲン検査に加え、MRI検査を受けられるように、主治医と相談していきましょう。
※「むちうち」という言葉について
「むちうち」という言葉は正式な病名ではなく、あくまで一般的な呼び名(俗語)です。
医療機関における正式な診断名は、「外傷性頚部症候群」となります。
3-3.症状が持続するため一定の期間病院へ通院している
後遺障害等級認定の申請を検討されている方は、必ず病院に通院してください。むちうちや外傷性頚部症候群の場合、通院期間が2〜3ヵ月と短いと後遺障害が認定されにくくなるためです。
交通事故の後遺障害認定は、紙ベースの資料を基準におこなわれ、交通事故被害者(患者)との面談はおこなわれません。そのため、通院期間や通院頻度で症状の程度が、後遺障害等級の認定を左右する大きな要素となっている可能性が高いのです。
3-4.適度な頻度で通院を続ける
通院をする際は、適度な頻度で続けるようにしてください。
通院期間と同様に、通院頻度も後遺障害認定は紙ベースでの認定実務に影響していると推測されます。主治医の先生と相談しながら、しっかりと適度な通院頻度で通院を続けることが重要です。
また、整形外科の医師でも交通事故診療をよく理解している医師とあまり理解していない医師がいます。そのため、交通事故診療をよく理解している主治医を見つけて通院を続けることも大切になるでしょう。
3-5.残存した症状の証明となる適切な書類を準備する
後遺障害認定を申請する際は、症状を証明するための適切な書類を準備しましょう。
残存した症状の証明となる最も重要な書類は後遺障害診断書ですが、実は医師は後遺障害診断書の適切な書き方を教わってはいないのです。そのため、医師によって後遺障害診断書の書き方が異なり、後遺障害認定に必要な内容が記載されないということが起こり得ます。
したがって、後遺障害診断書を作成してもらう際は、以下の点を意識するようにしてください。
- 現在の症状をしっかりと伝えて主治医にしっかり記載してもらう
- 症状固定時には主治医にしっかり症状を伝えて、後遺障害診断書に症状を記載してもらう
- レントゲン・CT・MRIの画像検査の異常所見・スパーリングテスト・ジャクソンテスト・腱反射などの神経学的異常所見といった他覚的所見がある場合は、その内容も後遺障害診断書に記載してもう
- 関節可動域の制限がある場合は、健側と患側の両方の可動域を必ず自動運動と他動運動で測定してもらい、記載してもらう
後遺障害診断書に症状が記載されていないと、一貫して症状が持続していないと判断される傾向にあります。そのため、症状に関する記載は特に確認するようにしてください。
関連記事:症状固定とは?定義や重要性・誰が決めるのか・症状固定後の対応
3-6.事前認定ではなく被害者請求をおこなう
後遺障害の認定には、事前認定と被害者請求の2種類の方法があります。
事前認定は、加害者側の保険会社に書類を提出する方法です。対して被害者請求は、被害者自身が書類を揃えて提出する方法です。
被害者請求は、自身で必要な書類を集める必要があるため手間がかかる一方で、十分な医学的証拠を集められることから、納得できる結果を得られる可能性が高いといえます。
関連記事:後遺障害の事前認定とは?メリット・デメリットや異議申し立ての方法
4.しびれで後遺障害14級が認定されるための具体的な症状や検査・所見
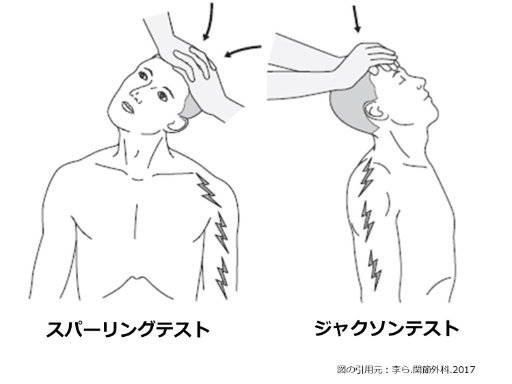
画像引用元:関節外科(メジカルビュー社)
しびれが後遺障害14級に認定されるためには、特定の症状や検査結果が重要です。交通事故後に上肢や下肢のしびれや痛みが持続している場合は、MRIやレントゲンなどの画像検査で明確な異常が確認できない場合でも、神経学的検査で異常が認められることがあります。
たとえば、頚部痛や上肢の痛み・痺れなどが継続していて、スパーリングテストやジャクソンテストなどの検査結果が陽性となる場合です。
また、通院状況や治療経過も重要な評価対象となります。
一定頻度以上の通院を一定期間以上継続しなければならない場合、症状の一貫性を示す要素となります。
後遺障害14級の具体的な認定基準は非公表でありブラックボックスとなっており、実際のところは調査をする担当者や担当部署しか知ることはできません。これらを総合的に判断し、後遺障害14級の認定がおこなわれていると予測されるのです。
5.【弁護士の先生へ】弊社はしびれによる後遺障害14級の認定をサポートします
合同会社ホワイトメディカルコンサルティングでは、弁護士の先生方向けに「カルテ画像精査・画像鑑定医」や「医学意見書作成」などのサービスを提供しております。
交通事故や労災などの案件で医学的証拠が必要になった場合は、ぜひ弊社へご依頼ください。
5-1.カルテ画像精査・画像鑑定
弊社では、カルテ画像精査・画像鑑定をおこなっています。各分野に精通した専門医によって、医療記録や画像診断結果(X線・CT・MRIなど)を詳細に分析し、後遺障害等級認定に有利になる情報を抽出します。
専門家の視点からカルテを精査し、弁護士の先生方のサポートをおこないますので、お気軽にご相談ください。
5-2.医学意見書作成
医学意見書は、外傷や疾患の状態について医師が専門的な見解を記述した文書です。主に交通事故や労災事故の後遺障害認定、医療訴訟、遺言能力の争いなどで使用されます。
この文書は、主治医ではなく、第三者の専門医が中立な立場で作成する書類です。そのため医学的証拠としての信頼性と価値が高まり、事故後の賠償請求や裁判における重要な医学的証拠となります。
弊社専門医が各事案において医学論文や医学書をいくつか引用しながら深堀りし、医学意見書を作成します。
また弊社には、ほぼすべての診療科の専門医が在籍しており、医学意見書作成に最適な診療科の選定は医師がおこないます。そのため、症状に関する客観的で正確な判断が可能です。
医学意見書作成をご検討の際は、ぜひ弊社までご相談ください。
※弊社は弁護士の先生からのお問い合わせに対してのみ、サービスを承っております。そのため事故の被害にあった当事者の方は、必ず代理人弁護士の先生を通してご連絡頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。
6.弊社の支援によって後遺障害14級が認定された事例
弊社の支援により、外傷性頚部症候群で非該当だった事案が14級と認定されました。
交通事故後により外傷性頚部症候群により頚部痛や上肢のしびれが出現し、持続・残存した事案で非該当だった事案が、弊社カルテ画像精査回答書・画像鑑定をさせていただいたことにより、14級と認定されました。
弊社のカルテ画像精査や医学意見書は、後遺障害の認定結果に対する異議申し立て時に大きな役割をはたします。認定の結果に納得がいかず異議申し立てを検討されている方は、ぜひ合同会社ホワイトメディカルコンサルティングまでご相談ください。
7.まとめ
交通事故や仕事中の事故などによって、上肢や下肢にしびれが残ることがあります。しびれの症状が長引き症状固定と判断された場合は、後遺障害14級に認定される場合もあるのです。
しびれで後遺障害14級が認められるためには以下のポイントが重要です。
- しびれの症状と事故との因果関係がはっきりしている
- 医学的・他覚的な検査がしっかりされている
- 症状が持続するため一定の期間病院へ通院している
- 適度な頻度で通院を続ける
- 残存した症状の証明となる適切な書類を準備する
- 事前認定ではなく被害者請求をおこなう
また、被害者請求によって後遺障害等級認定を受ける方は、医学意見書を準備しておくのもおすすめです。
合同会社ホワイトメディカルコンサルティングでは、後遺障害認定の被害者請求時に有効な証拠となる医学意見書の作成をおこなっております。
しびれによる後遺障害を抱え医学意見書が必要な状況にある方は、是非弊社にご依頼ください。
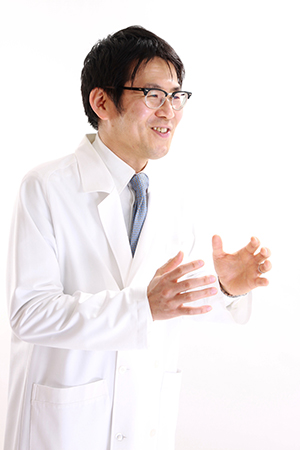
このコラムの著者
白井 康裕
【経歴・資格】
・日本専門医機構認定 整形外科専門医
・日本職業災害医学会認定 労災補償指導医
・日本リハビリテーション医学会 認定臨床医
・身体障害者福祉法 指定医
・医学博士
・日本整形外科学会 認定リウマチ医
・日本整形外科学会 認定スポーツ医
2005年 名古屋市立大学医学部卒業。
合同会社ホワイトメディカルコンサルティング 代表社員。
医療鑑定・医療コンサルティング会社である合同会社ホワイトメディカルコンサルティングを運営して弁護士の医学的な業務をサポートしている。
【専門分野】
整形外科領域の画像診断、小児整形外科、下肢関節疾患