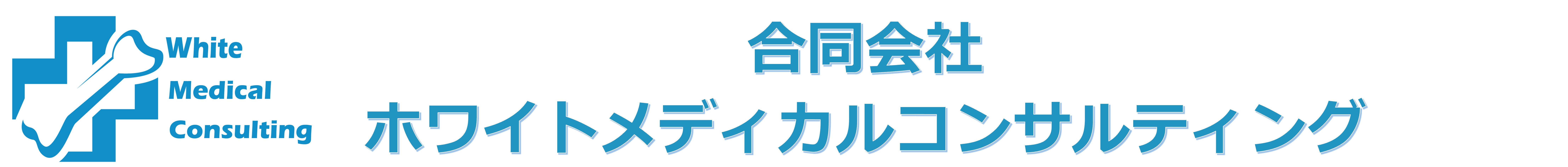後遺障害等級認定の期間とは?目安より遅れる理由や対処法も解説

「後遺障害等級認定にかかる期間ってどのくらい?」と疑問に思っていませんか?すでに手続きを進めていて、認定結果の通知が遅く不安に思われている方もいるかもしれません。
そこでこの記事では、以下の内容について解説していきます。
- 後遺障害等級認定にかかる期間の目安
- 後遺障害等級認定の流れ
- 後遺障害等級の認定が遅くなる理由や原因
- 後遺障害等級の認定が遅くなるリスク・注意点
- 後遺障害等級の認定が遅れているときの対処法
この記事を読むことで、後遺障害等級認定の期間だけでなく、手続きが遅延しているときの対処法まで理解できます。後遺障害等級認定の手続きの進捗を不安に思われている方は、ぜひ最後までご覧ください。
1.後遺障害等級認定にかかる期間の目安
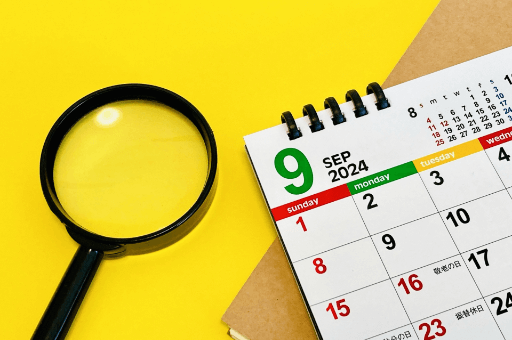
後遺障害等級認定の結果が出るまでの期間は、通常1カ月から2カ月とされています。
損害保険料率算出機構が発表しているデータによれば、約87%のケースが60日以内に調査を終了しています。
| 調査期間 | 全体に対する割合 |
| 30日以内 | 73.7% |
| 60日以内 | 14.0% |
| 90日以内 | 6.7% |
| 90日超 | 5.6% |
参考:自動車保険の概況 2023年度版(2024年4月発行)
ただし、書類の不備や医療照会の回答遅れなどが原因でさらに時間がかかる場合があります。またこの調査期間はあくまで自賠責保険から損害調査事務所に書類が送られてから、損害調査事務所内での調査が終了するまでの期間です。
そして、高次脳機能障害などの複雑なケースでは、審査が長引くこともあり、認定結果が出るまでに半年から1年程度を要することもある点には注意が必要です。
2.後遺障害等級認定の流れ
後遺障害等級認定の手続きには、以下の2種類があります。
- 事前認定
- 被害者請求
ここからは、それぞれの手続きの流れについて解説していきます。
2-1.事前認定の流れ
事前認定は、加害者側の任意保険会社を通じて後遺障害等級の認定を申請する方法です。
個人の対応としては、被害者が医師に後遺障害診断書を作成してもらい、それを任意保険会社に提出するのみで終了します。その後、保険会社が必要な書類を揃え、自賠責保険に対して後遺障害等級の認定を申請するという流れです。
この方法は、被害者の手間が少ない反面、保険会社任せになるため、適切な等級認定が受けられない可能性があります。
関連記事:後遺障害の事前認定とは?メリット・デメリットや異議申し立ての方法
2-2.被害者請求の流れ
被害者請求は、被害者自身が必要な書類を揃えて、自賠責保険に対して直接後遺障害等級の認定を申請する方法です。以下の流れで進んでいきます。
- 医師に後遺障害診断書を作成してもらう
- 交通事故証明書、診療報酬明細書、事故発生状況報告書などの必要書類を揃える
- 準備した書類を自賠責保険会社に提出する
- 損害保険料率算出機構が審査をおこなう
被害者請求は手間がかかりますが、必要な資料を漏れなく提出できるため、適切な等級認定が受けられる可能性が高まるのが特徴です。
3.後遺障害等級の認定が遅くなる理由や原因
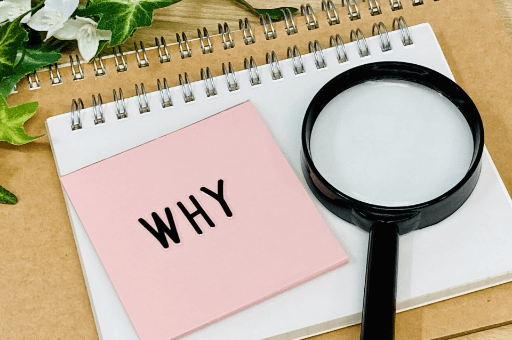
後遺障害等級の認定に関する手続きを進める中で、結果が出るまで時間がかかるケースも少なくありません。その理由や原因としては、以下の5点があげられます。
- 保険会社での手続きが遅れている
- 病院の対応が進んでいない
- 損害保険料率算出機構による調査が難航している
- 評価が難しい症状の申請をしている
- 提出書類に不備がある
それぞれみていきましょう。
3-1.保険会社での手続きが遅れている
後遺障害等級の認定が遅れる主な原因の一つは、保険会社における手続きの遅延です。
保険会社は、被害者が受け取るべき保険金の支払いをおこなうため、必要な書類や情報を収集し、審査をおこないます。しかし、これらの手続きが滞ると、認定までの期間が延びてしまうのです。
特に、必要書類の確認や追加資料の請求に時間がかかる場合があります。
3-2.病院の対応が進んでいない
後遺障害の認定には、医療機関からの詳細な診断書や検査結果が必要です。病院側の対応が遅れると、詳細な資料の取得に時間がかかり、結果として認定手続き全体が遅れてしまいます。
医師が多忙であったり、診断書作成の優先度が低かったりといった理由が考えられます。
3-3.損害保険料率算出機構による調査が難航している
損害保険料率算出機構は、後遺障害等級認定において専門的な調査や評価をおこなう機関です。損害保険料率算出機構での調査が複雑で時間がかかる場合、認定までの期間が延びる原因となります。
特に、症状の特異性や複雑性が高い場合、詳細な調査が必要となり、時間を要することがあります。
3-4.評価が難しい症状の申請をしている
後遺障害のなかには、適切な評価が難しい症状も存在します。たとえば、痛みや感覚障害など、客観的な証拠が取りにくい症状の場合、認定基準に適合させるための資料収集や説明に時間を要することがあるのです。
このようなケースでは、認定までの期間が長引く傾向があります。
3-5.提出書類に不備がある
提出書類に不備や不足があると、再提出や追加資料の提出が必要となり、認定手続きが遅れる原因となります。必要書類が多くなる被害者請求では、書類の記載漏れや必要な証拠資料の欠如などが起きがちです。
手続きをスムーズに進めるためには、提出前に書類の内容や必要書類を十分に確認することが重要です。
4.後遺障害等級の認定が遅くなるリスク・注意点
では、後遺障害等級の認定に時間がかかることにはどのようなリスク・注意点があるのでしょうか。以下の2点を解説していきます。
- 後遺障害等級認定や損害賠償請求には時効がある
- 示談金の受け取りが遅れる
それぞれみていきましょう。
4-1.後遺障害等級認定や損害賠償請求には時効がある
後遺障害等級認定や損害賠償請求には、法定の「時効」が設けられています。定められた時効までに手続きが終了しない場合、法的な権利を失うことになり、後遺障害や損害賠償を求めることができなくなってしまいます。
たとえば、労災による障害(補償)給付請求の時効は、症状固定した日の翌日から5年以内と定められています。したがって、症状固定と診断されたら、速やかに請求手続きを進めることが重要です。
関連記事:症状固定とは?定義や重要性・誰が決めるのか・症状固定後の対応
4-2.示談金の受け取りが遅れる
後遺障害等級の認定が遅れると、示談金の受け取りも遅延する可能性があります。示談金は、後遺障害等級の認定結果を基に算定されるため、認定が完了しない限り、金額の確定や支払い手続きが進みません。
治療費が高額な場合、示談金の受け取り遅延によって治療後の生活費に影響を及ぼす可能性も否定できません。
5.後遺障害等級の認定が遅れているときの対処法

後遺障害等級の認定が遅れていると思ったら、以下3つの対処法を実践してみてください。
- 保険会社に対し定期的に連絡する
- 弁護士に相談する
- 被害者請求に切り替える
一つずつ確認し、少しでも早く認定を受けられるようにしましょう。
5-1.保険会社に対し定期的に連絡する
まずは、保険会社に定期的な連絡をおこなってください。逐一手続きの進捗状況を把握し、不明な点や問題があれば早期に解決することが大切です。
また、連絡を通じて、必要な書類や情報の提出漏れを防ぐことも可能です。
5-2.弁護士に相談する
後遺障害等級の認定が長引く場合、専門知識を持つ弁護士に相談することが有効です。弁護士は、法的な手続きや交渉に精通しており、適切なアドバイスやサポートをしてくれます。
特に、保険会社との交渉や、必要な書類の整備に関して専門的な支援を受けることで、認定までの期間を短縮できる可能性が高いです。
5-3.被害者請求に切り替える
事前認定で手続きを進めている方は、加害者側の保険会社任せではなく、自身で手続きをおこなう被害者請求に切り替えることも検討できます。
被害者請求であれば、必要な書類や証拠を自分で収集・提出でき、認定手続きの進行状況を直接管理できます。
5-3-1.弁護士に依頼することでさらなる期間短縮になる
被害者請求には専門的な知識や手続きが伴うため、弁護士などの専門家に相談することが望ましいです。
弁護士に依頼することで、後遺障害等級認定の手続きがスムーズに進み、期間短縮が期待できます。また、保険会社との交渉を代行してくれるため、手続きの負担も軽くなります。
6.異議申し立ては早めにおこなう
後遺障害等級認定の結果に対して納得できない場合、異議申し立てによって障害の程度に対する認定結果に異議を唱え、再評価を求めることが可能です。
異議申し立ては、後遺障害等級認定をおこなった損害保険料率算出機構や自賠責保険に対しておこないます。
異議申し立ての主なポイントは、以下の3点です。
- 異議申し立てをおこなうにあたり、新たな医学的証拠や資料の提出が重要
- 手続きや必要書類は、各保険会社や関連機関によって異なる場合がある
- 後遺障害等級認定や損害賠償の時効に間にあるよう手続きを進める必要がある
後遺障害等級認定同様に、異議申し立てをおこなう際も時効には十分注意してください。
関連記事:後遺障害が認定されない理由とは?認定されなかったときの対処法も解説
6-1.異議申し立て時の医学的証拠は弊社までご相談ください
異議申し立てをおこなう際は、最初の後遺障害等級認定の手続きよりもさらに詳細な医学的証拠を用意しましょう。異議申し立てにおいては、客観的な証拠に基づいて異議を唱え、正当な主張であることを示す必要があります。
医学的証拠として有効なものが、医学意見書です。医学意見書とは、医師・専門医が病状、治療、予後などについて、医学的な見解を詳細に記述した文書のことです。
医学意見書によって、主治医ではない第三者の専門医による見解が示されるため、異議申し立てでは重要な役割を果たします。
弊社には、ほぼすべての診療科の専門医が在籍しており、医学意見書作成に最適な診療科の選定は医師がおこないます。そのため、症状に関する客観的で正確な判断が可能です。
医学意見書作成をご検討の際は、ぜひ弊社にご相談ください。
※弊社は弁護士の先生からのお問い合わせに対してのみ、サービスを承っております。そのため事故の被害にあった当事者の方は、必ず代理人弁護士の先生を通してご連絡頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。
7.まとめ
後遺障害等級認定において、損害調査事務所内での調査が終了するまでの期間は、60日以内のケースが多いです。そこに手続き開始までの期間や結果通知までの期間などが追加され、全体ではもう少し長い期間を要します。
また、保険会社や医療機関での対応が遅れたり、評価の難しい症例だったりする場合、後遺障害の等級を認定されるまでの期間がさらに伸びる可能性もあります。
もし後遺障害等級認定に時間がかかりすぎていると感じた場合は、以下3つの対処法を試してみてください。
- 保険会社に対し定期的に連絡する
- 弁護士に相談する
- 被害者請求に切り替える
合同会社ホワイトメディカルコンサルティングでは、後遺障害認定の被害者請求時に有効な証拠となる医学意見書の作成をおこなっております。
後遺障害を抱え医学意見書が必要な状況にある方は、是非弊社にご依頼ください。
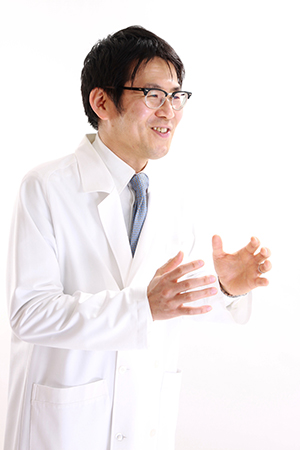
このコラムの著者
白井 康裕
【経歴・資格】
・日本専門医機構認定 整形外科専門医
・日本職業災害医学会認定 労災補償指導医
・日本リハビリテーション医学会 認定臨床医
・身体障害者福祉法 指定医
・医学博士
・日本整形外科学会 認定リウマチ医
・日本整形外科学会 認定スポーツ医
2005年 名古屋市立大学医学部卒業。
合同会社ホワイトメディカルコンサルティング 代表社員。
医療鑑定・医療コンサルティング会社である合同会社ホワイトメディカルコンサルティングを運営して弁護士の医学的な業務をサポートしている。
【専門分野】
整形外科領域の画像診断、小児整形外科、下肢関節疾患